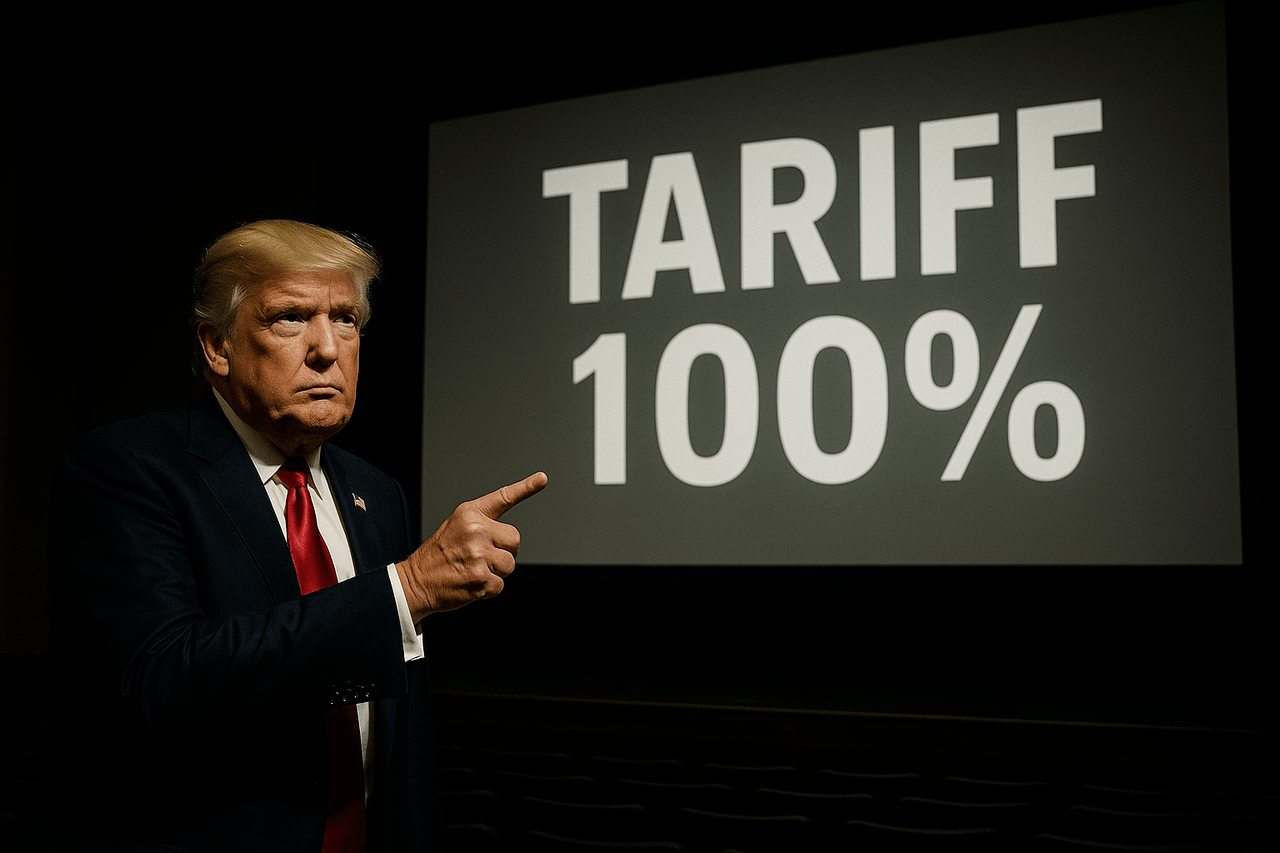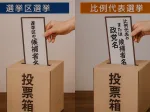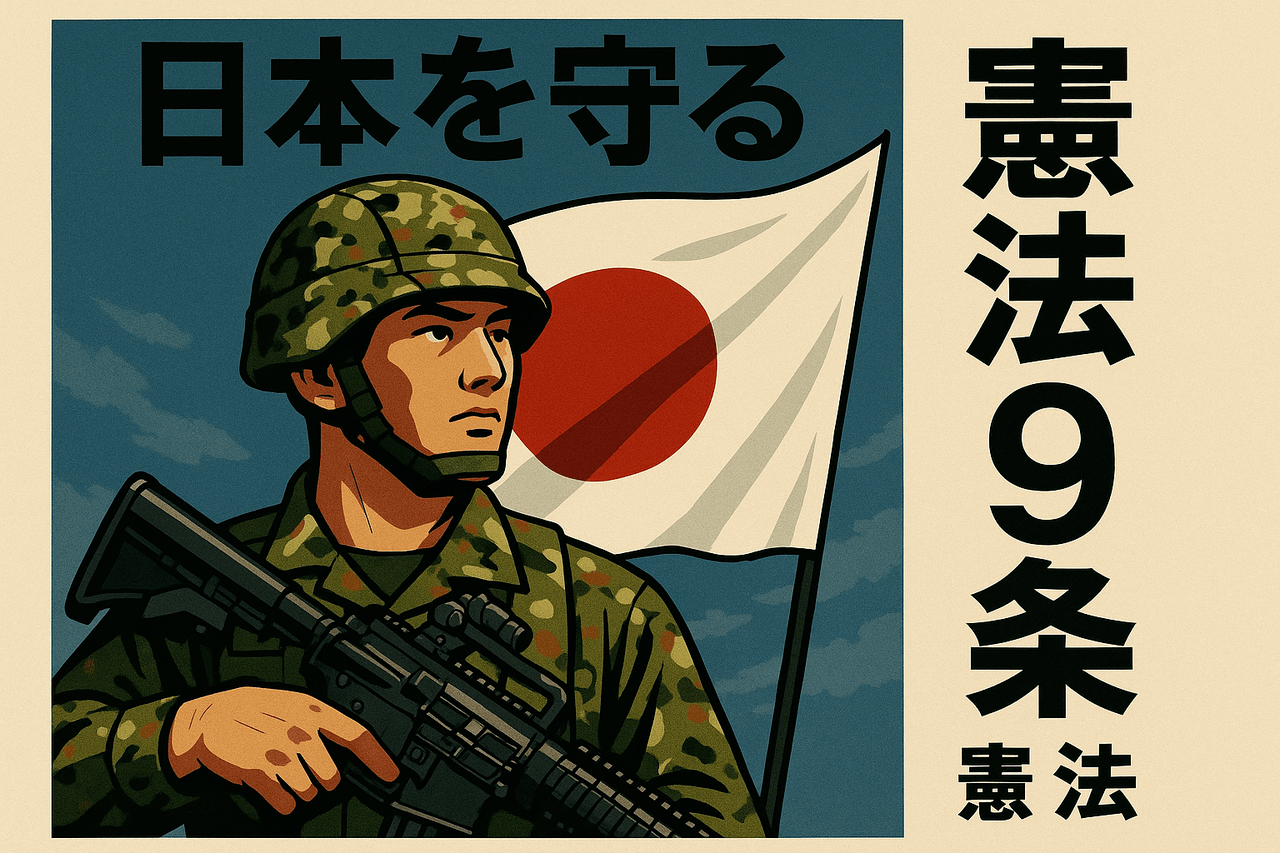日本では毎年多くの子どもたちが行方不明になっています。警察庁の統計によると、2023年には9歳以下の行方不明者が1,115人に達し、これは前年より50人以上増加した数字です。
行方不明となる子どもの数は年々高止まりし、事件の背景や社会的な関心にも影響を与えています。
多くのケースが未解決であり、依然としてその多くがメディアで十分に取り上げられていない現実があります。この記事では、子どもの行方不明の現状、背景、そしてメディアの役割について掘り下げていきます。
行方不明の現状
日本では毎年約8万人が行方不明となり、その中で9歳以下の子どもたちも多数含まれています。
警察庁の統計によると、令和2年(2020年)には7万7,000件の行方不明が報告され、うち9歳以下は1,055人にのぼりました。
毎年、行方不明者の数は8万件前後で推移しており、子どもたちの行方不明が大きな社会問題となっています。
多くの事例は数日以内に解決しますが、行方不明になったままのケースも存在し、長期間にわたって家族や社会に深い影響を与え続けています。
行方不明の原因と背景
行方不明者の原因として、さまざまな理由が考えられます。
まず、「疾病関係」が最も多く、全体の3割を占めています。特に認知症の疑いがある高齢者が行方不明になるケースが目立ちます。
しかし、未成年の子どもに関しては、誘拐や監禁といった事件性が関わることもあります。
過去には新潟県三条市で9歳の女児が中年男性に監禁された事件や、埼玉県朝霞市で13歳の少女が大学生に誘拐され監禁された事件などがあり、社会を震撼させました。
また、未成年者の行方不明については、家庭問題や学校でのトラブル、あるいは家出なども大きな要因として挙げられます。
こうした背景は、子どもたちが一時的に家を離れることを引き起こし、その結果、行方不明となるケースを生むことがあります。
メディアの報道の現状と課題
しかし、こうした事件はメディアに十分に報じられているとは言えません。行方不明となった子どもたちの多くは数日以内に帰宅したり、警察によって見つかったりしますが、事件性が薄いと判断されると報道が控えめになることがあります。
特に、家出や一時的な家族の問題で行方不明となった子どもたちは、誘拐事件や重大な犯罪として扱われないことが多いため、報道が少なくなりがちです。
例えば、山梨県道志村で行方不明となった小倉美咲ちゃん(9歳)のケースでは、2019年9月21日に家族とキャンプに訪れていた際に姿を消しました。
母親が一瞬目を離した隙に消えた美咲ちゃんは、その後も見つかっていませんが、メディアの報道は次第に減少し、世間の関心も薄れていったことが、親であるとも子さんにとっては深い痛手となっています。
とも子さんは、毎月山梨に通いながら情報提供を呼びかける活動を続けていますが、報道が少なくなる中での孤独感を感じていると語っています。
行方不明の子どもたちの事件は、長期にわたり解決しない場合、その後の報道が途絶えてしまうことが多いのです。
結果として、社会全体の関心が薄れてしまい、再発防止や支援の呼びかけが十分に行われなくなることが懸念されます。
行方不明者への二次被害
行方不明となった子どもたちに対しては、単に行方を追うだけではなく、家族に対しての支援も重要です。行方不明事件では、子どもを探している家族が誹謗中傷を受けることもあります。美咲ちゃんの母親とも子さんは、事件発生から長期間にわたってネット上での誹謗中傷にさらされています。
さらに、行方不明事件の親が詐欺に巻き込まれることもあります。大阪府で行方不明となった吉川友梨ちゃん(当時10歳)の両親は、事件後に「友梨ちゃんを見つけた」と言って近づいてきた人物に騙され、数千万を詐取されるという二次被害を受けました。こうした精神的・経済的な苦しみは、失われた子どもへの思いと相まって、家族にとっては大きな負担となります。
親たちの苦悩と社会の無関心
行方不明の子どもの親たちは、社会の無関心や誹謗中傷に悩まされています。吉川友梨ちゃんの両親も、メディアからの取材を断るようになりました。詐欺被害に遭ったことが原因で、他者への不信感が強まり、取材を拒否するようになったのです。このような精神的な苦痛が続く中で、メディアや社会の関心が薄れることは、さらに深刻な問題を引き起こします。
親たちは、自分の子どもが行方不明になったことに対して深いショックを受けるだけでなく、さらにその後の不正行為や中傷に苦しむことになります。この苦しみが長期間続く中で、社会全体のサポートが不足している現状は深刻な問題です。
行方不明の子どもを守るために
行方不明事件を減らすためには、家庭や学校での防犯教育が不可欠です。特に、子どもたちが危険な状況に巻き込まれないよう、日常的に注意喚起を行い、どうすれば安全に生活できるかを教えることが大切です。また、地域社会が協力して、子どもたちが安心して過ごせる環境を作ることも重要です。
さらに、メディアはこの問題をもっと取り上げ、社会全体で解決策を考えていく必要があります。行方不明の子どもたちが1人でも減るように、今後は報道のあり方を再考し、社会全体で支え合っていくことが求められています。