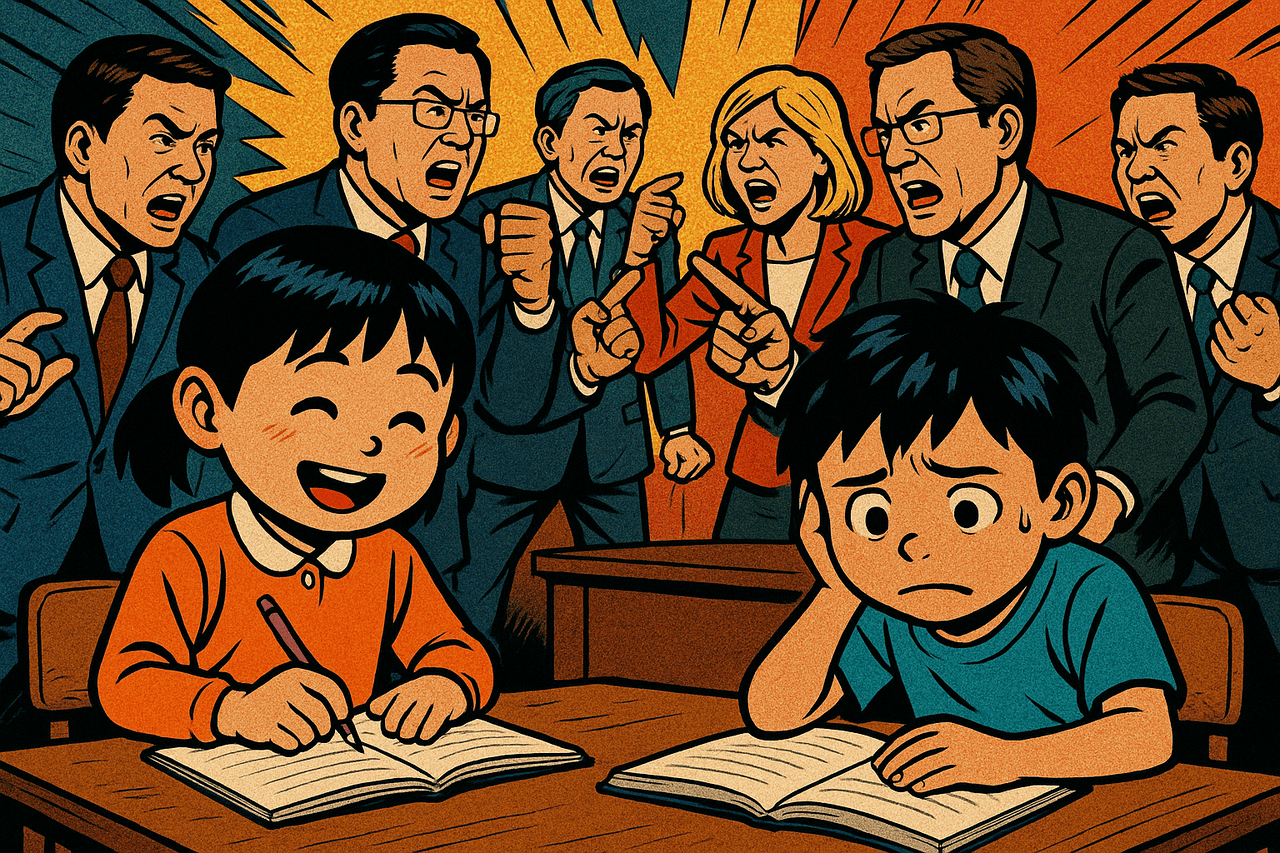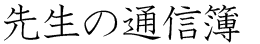日本にエボラを?致死性ウイルス輸入の裏側に広がる不安
「オリンピック対策」の名目で危険ウイルスを日本国内に
2020年東京オリンピックを前に、日本政府がひそかに進めた政策が今、大きな波紋を呼んでいる。エボラ出血熱やマールブルグ病など、致死率が高く扱いの難しい5種の病原体を、国立感染症研究所(東京都武蔵村山市)にあるBSL-4(バイオセーフティーレベル4)施設へ輸入・保管した件だ。
政府の説明は、「五輪開催中に感染症が発生した場合の備えとして、検査体制を強化する必要があった」というものだ。これらのウイルスは生きた状態でなければ検査技術の実証ができないとされ、厚労省は「研究目的の輸入」と正当性を強調する。
しかし、問題はそのプロセスにある。地元住民の合意が十分に得られないまま、国家主導で最も危険な病原体が都心に搬入されたのだ。しかも、長らく稼働が凍結されていたBSL-4施設を、2015年の厚労省と市長との協定をもって急遽稼働再開させた背景には、地域の声よりも国家的イベントを優先する姿勢が透けて見える。
感染研の西條政幸部長は、「日本の研究体制を世界水準に引き上げるための画期的な一歩」と語るが、現場に暮らす市民にとっては「不安の塊」でしかない。
国民不在の科学政策 「安心・安全」より「先進国アピール」?
実際、米国や欧州ではすでに複数のBSL-4施設が稼働しており、中国でも武漢を含めた5施設体制の整備が進んでいる。それに対し、日本は長らく「ゼロ」に近い状態だった。だからといって、なぜこのタイミングで、なぜ人口密集地に設置する必要があったのか?
SNSでは、
「わざと危険ウイルスを“お漏らし”して、緊急事態条項発動の口実にするつもりでは?」
「都心でやる意味がわからない。むしろ脅しに見える」
「長崎にもBSL-4作るって正気?」
といった疑念や批判の声が相次いでいる。
長崎大学にも同様のBSL-4施設建設計画が進んでいるが、周辺住民からは避難計画や安全基準が未整備であることを理由に、反対運動が起きている。
一方、バイオセキュリティーの第一人者であるリチャード・エブライト氏(米ラトガース大学)は、「高度な実験室があればウイルスの保管なしでもシミュレーション研究は可能」と指摘。さらに「実際に危険ウイルスを保管することで、偶発的漏洩や悪意ある利用のリスクはむしろ高くなる」と強く警鐘を鳴らす。
こうした指摘にもかかわらず、研究施設側は「安全性は確保されている」「世界標準に追いつくために不可欠」と反論するばかり。市民との対話を避けるその姿勢自体が、信頼を大きく損なっているのだ。
科学の暴走が引き起こすもの 日本に求められる“説明責任”
技術の進歩や国際競争力の強化は確かに必要だ。しかし、リスクの高い研究においては、それ以上に説明責任や合意形成が重要だ。
「万が一」が起こったとき、責任は誰が取るのか?
災害大国・日本において、高リスクの施設をわざわざ都市部に置くことの是非は、今改めて問われている。
オリンピックは終わった。だが、輸入されたウイルスはそのまま国内に残され、研究は今も続いている。
検査技術の精度向上や感染症対策の強化を否定するつもりはない。だが、「研究のため」という大義名分があれば、どんなリスクでも正当化されるのだろうか。
市民が知らぬ間に命のリスクを背負わされている――そう感じている人が少なくないのも無理はない。
科学と行政の暴走を許さないために、今こそ「声なき声」に耳を傾けるべきだ。
感染研や厚労省には、専門家の権威に頼るだけでなく、住民との誠実な対話と、徹底した情報公開こそが求められている。
参考サイト
<a href="https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v17/n1/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%8C%E8%87%B4%E6%AD%BB%E6%80%A7%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%92%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1/101651" target="_blank" rel="noopener" title="">日本が致死性ウイルスを輸入した理由</a>