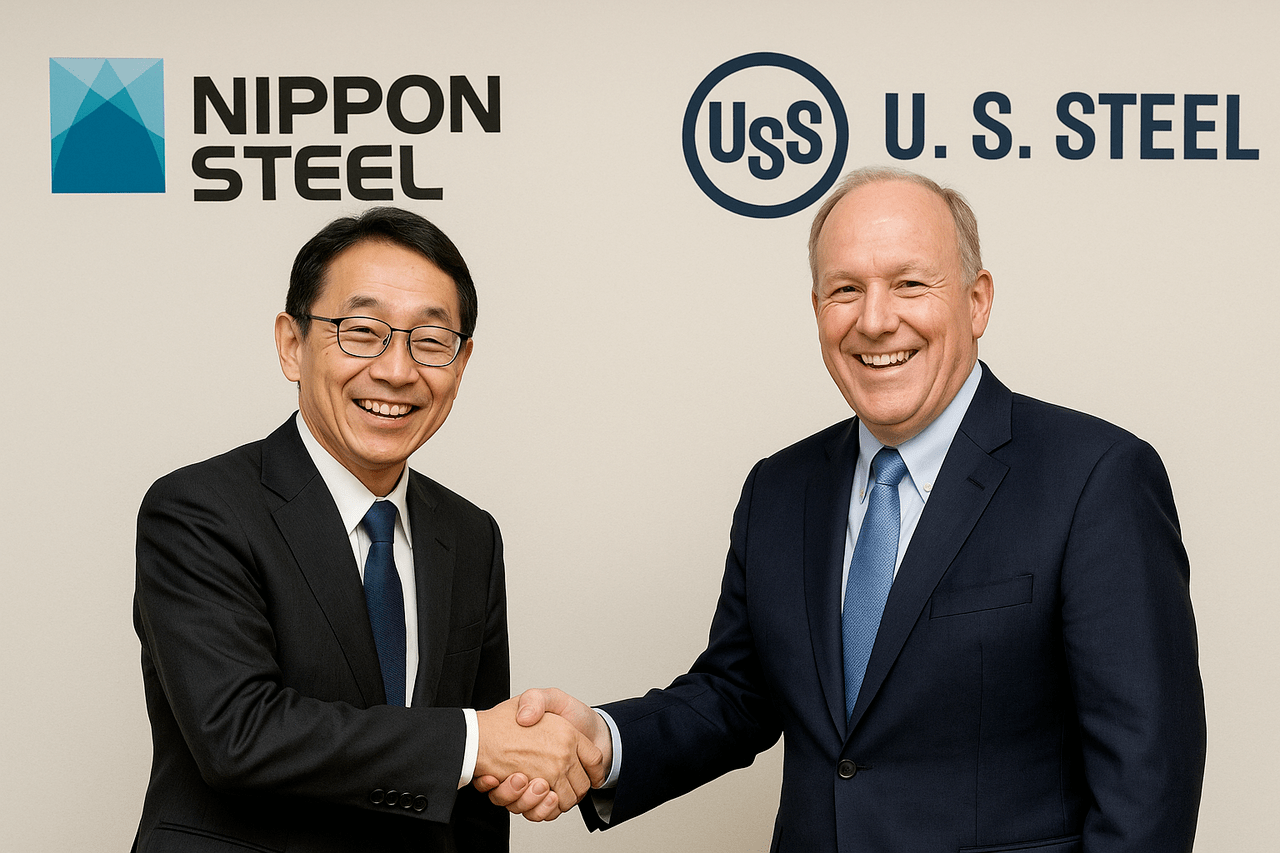日本のODA支出、過去10年で倍増 国民負担が増す中でも海外援助は右肩上がり
- 2025/6/14
- 記事

日本の「失われた30年」とODAのジレンマ
日本は1990年のバブル崩壊以降、長らく経済成長が停滞し、失われた30年を経験してきました。名目GDPは約5.5兆ドルから4.2兆ドルへと縮小し、実質賃金も11%ほど落ち込んでいます。家計は痛みを伴い、若い世代や非正規労働者を中心に、「将来に見通しが立たない」と嘆く声が社会の隅々に広がっています 。
さらに進む高齢化。2022年には65歳以上が人口の約29%を占め、将来的には人口減による社会保障の圧迫が深刻化する見通しです 。その一方で、経済は2025年第1四半期に年率‐0.7%のマイナス成長を記録。個人消費や輸出が停滞し、国内の買い物すら腰が重い状況が続いています 。
国民は苦しいのに、ODAは右肩上がり
そんな中、政府開発援助(ODA)は着実に増加を続けています。以下は、過去10年間の推移です。
| 年度 | 総支出額 |
|---|---|
| 2015年 | 15028 M USD (18.19兆円) |
| 2016年 | 16808 M USD (18.29兆円) |
| 2017年 | 18461 M USD (20.71兆円) |
| 2018年 | 17250 M USD (19.05兆円) |
| 2019年 | 18923 M USD (20.63兆円) |
| 2020年 | 20304 M USD (21.68兆円) |
| 2021年 | 21953 M USD (24.1兆円) |
| 2022年 | 22263 M USD (29.27兆円) |
| 2023年 | 24001 M USD (33.73兆円) |
一方で、家計は膨大な社会保障負担と年金問題に疲弊しています。「失われた世代」と呼ばれる若者や、非正規で低賃金に甘んじている人々には、「どうして自分たちの生活をほったらかしにして、海外にお金が流れるのか」という疑問が消えません。
なぜODAは増え続けるのか?政府の“理由”と市民の反応
戦略的外交と「リアリズム外交」
自民党政権は、ODAをインド太平洋構想や気候変動対策、インフラ整備などに充て、外交・安全保障の一手として積極活用しています 。国際社会での影響力維持を図り、中国との競争に対応する「戦略ツール」と捉えているわけです。
国内でも賛否の声
ODA大綱の見直しにより、かつての「人道支援」から「国益志向」への転換が明らかになりました。2003年からの改定で「我が国にも利益をもたらす」という表現が明記され、国民の賛同率は低下しました。
支持する意見もある一方で、経済論者や市民団体からは「国内優先が先」「税金の使い方に疑問」といった批判が根強く、「援助は企業側の利益や外交目的によるものではないか」と監視の目が向けられています 。
国民の生活とODAの乖離が生む“違和感”
生活実感とのズレ
家計を直撃するのは、貧困、高齢者負担の増加、失業リスクです。そんな中、ODAに数兆円規模の予算が回されるのは、「暮らしの実感」と大きく掛け離れています。TwitterやSNSでは「自分たちの給料が上がらないのに、なぜ海外には使われるの?」という投稿が散見されます。
政府の言い訳と限界
政府は「グローバルな影響力維持」「人道・気候対応」を説明しますが、財政赤字と社会保障費の増大が叫ばれる中、国民には理解しがたいと言います。ODAを正当化しようとすればするほど、「内政放置」という批判が強まる悪循環に陥っています。
今後どうすべきか?バランスの取れた政策を求めて
成果の「見える化」
在外援助の使途や現地での成果を、子育て支援や介護と同じように可視化する仕組みが求められます。税金の流れがわかる情報公開は透明性の第一歩です。
国民との対話強化
予算編成や政策説明に市民の声を取り入れる対話の場を定期開催。SNSでも公開質疑などがあれば、理解と共感を得やすくなります。
国内支援との連動
賃金底上げや現役世代への支援をODAとセットで実行する。たとえば育児・介護の予算増とODA政策をパッケージで示せば、「片方だけ切り捨てる」との印象は薄れます。
ODAと国内政策、どちらも大切に
言ってしまえば、日本は「世界のためにも動きたい。でも国民が苦しい」。ODAは国益や国際貢献に役立ちますが、その負担を担うのは今の日本国民です。だからこそ、単に「増やす」ではなく、「どう使うか」「誰に説明するか」を国民が納得できる形に変える必要があります。
今後の日本にとって重要なのは、ODAと国内政策の“両立”。世界とのつながりと、国民一人ひとりの暮らしを両方支える政策運営に転換していかない限り、「国民が苦しんでいるのに海外ばかりを向いている」という印象は消えないでしょう。
石破政権がスリランカに90万ドル(約1.4億円)無償支援 地雷除去支援は総額73億円超、国内では反発の声