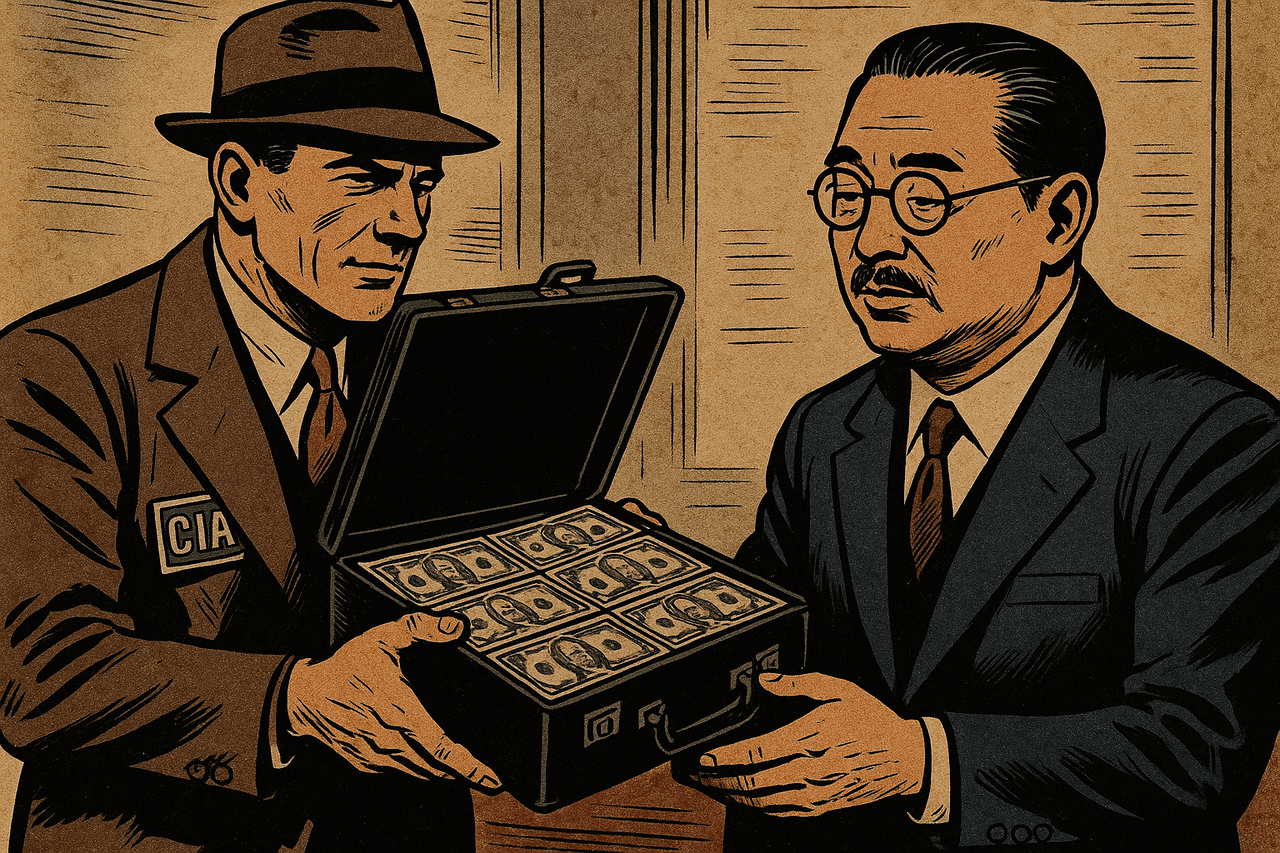【風力発電は本当に持続可能か?】事故多発と低効率で問われる再生可能エネルギーの現実
日本各地で導入が進む風力発電。しかし、その裏では、効率の低さや事故の多発といった深刻な課題が見え隠れしている。2025年5月、秋田市で発生した風力発電の羽根落下事故は、その危うさを改めて浮き彫りにした。
羽根落下事故で男性死亡 全国で相次ぐトラブル
5月2日、秋田市の海沿いの公園で、風車の羽根が突如落下。近くにいた81歳の男性が倒れているのが見つかり、間もなく死亡が確認された。男性は「タラの芽を採りに行く」と言って自転車で外出した直後だったという。現場付近は住民の散歩コースでもあり、「風車の下を歩くのは怖かった」と話す近隣住民の声もある。
風力発電に関わる事故は決して珍しくない。経済産業省のまとめによると、過去5年間で全国の風力発電設備に関連する事故は約200件に上り、そのうち約30件が羽根の破損によるものだった。羽根の先端は回転時に時速300キロに達し、砂や雨にさらされるため、損傷が生じやすい。放置すれば、今回のような落下事故につながる恐れがある。
風がなければ発電できない? 不安定な出力
風力発電は、太陽光や水力と並ぶ再生可能エネルギーとされるが、最大の弱点は「風まかせ」であること。風が吹かなければ発電はゼロに近く、逆に暴風が吹き荒れれば安全のため停止せざるを得ない。こうした不安定な出力は、安定供給が前提の電力網にとっては大きなリスクとなる。
実際、風力発電の設備利用率(稼働率)は平均で20%台にとどまる。つまり、100%中の2割程度しか実際には発電できていないのが現実だ。
設置も維持も高コスト 元は取れるのか
さらに問題となるのがコストだ。風力発電設備の設置には1kWあたり平均22万円がかかり、年間のメンテナンス費も1kWあたり0.6万円程度とされる。これに加え、老朽化した設備の交換や、倒壊・破損時の対応コストも馬鹿にならない。
海外製の大型風車を使っているケースも多く、部品の取り寄せや保守点検にも時間と費用がかかる。採算性の低さが、地域にとって持続可能な投資といえるのかどうか、疑問の声もあがっている。
政策で推進されるが…技術と安全体制は追いつかず
政府は「エネルギー基本計画」において、風力発電の電源構成比を現行の約1%から、2040年には4~8%に拡大する目標を掲げている。しかし、今回の事故のように、安全性への不安が拭えないまま設備だけが増えていくのでは、住民の信頼は得られない。
早稲田大学の小野田弘士教授(システムエネルギー工学)は「風車はどんどん大型化しており、事故が起きたときの被害も拡大する。国も事業者任せにせず、定期検査の徹底や事故原因の公開を進めるべきだ」と指摘する。
持続可能なエネルギー社会のために
温暖化対策として再生可能エネルギーの導入は急務だが、「安全」「安定」「経済性」の3条件を満たさなければ意味がない。風力発電は一見クリーンに見えて、その実、多くの問題を抱えている。
今後のエネルギー政策では、こうした現場の実態と技術的な限界を直視し、真に持続可能な道を探る必要がある。再生可能エネルギーへの過信は、時に命を奪う現実につながるということを、私たちは忘れてはならない。
参考サイト
<a href="https://www.yomiuri.co.jp/national/20250502-OYT1T50223/" target="_blank" rel="noopener" title="">風力発電事故5年で200件、羽根破損は30件…亡くなった男性「タラの芽採りに」自転車で外出</a>