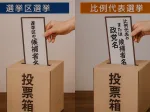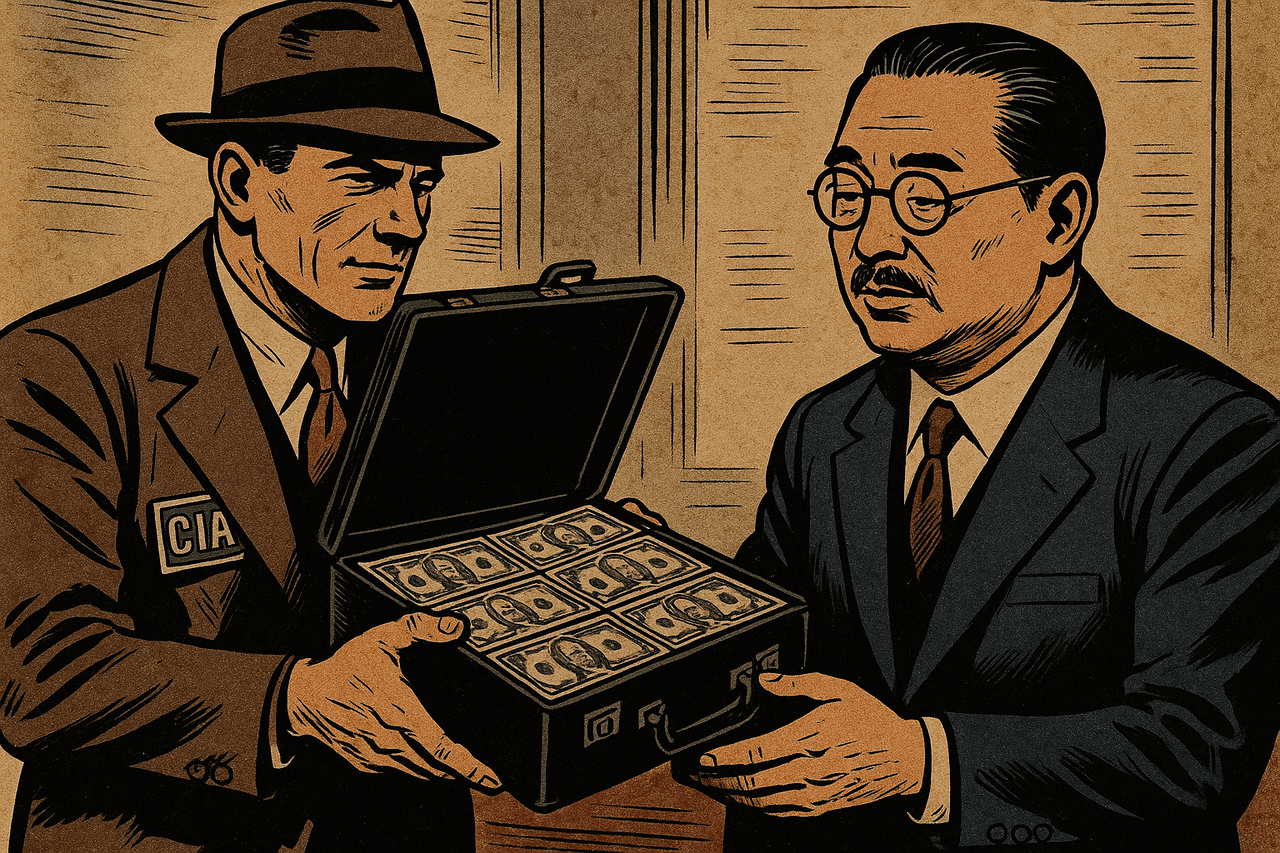目次
- 減税は日本経済の処方箋になるか?
- 「ケインズ的」発想はもう古い
- 減税はインフレを生むのか? 答えはノー
- 減税は「正しく使えば」インフレ抑制にもなりうる
- 財政赤字論の“呪い”から解放されよ
- 「誰にとってのインフレか」を問え
- 減税を恐れるな、インフレに騙されるな
減税は日本経済の処方箋になるか?
――インフレ恐怖と古い経済学から脱却を
私たちの暮らしは、年々重くなっている。
食料品、日用品、光熱費、ガソリン……。あらゆる物の値段がじわじわと上がる一方で、給料や手取りはほとんど増えない。多くの家庭が「節約だけでは乗り切れない」と感じているのが今の日本の現実だ。
こうした状況を受けて、「消費税を減税すべきだ」「ガソリン税の上乗せ(暫定税率)はもう不要だ」といった声が高まっている。だが一方で、これに対し「減税をすればインフレが加速し、かえって国民が苦しむ」「財政赤字が拡大する」といった“お決まりの反論”も根強い。
しかし、それらの主張はしばしば時代遅れの経済理論――特にケインズ経済学的な世界観に依存している。いま私たちが生きているのは、1930年代でも1970年代でもない。
構造が複雑化し、デジタル化と人口減少が進むこの国の経済を考えるなら、もっと現代的な経済の視点=近代経済学に基づいた議論が必要だ。
「ケインズ的」発想はもう古い
ケインズ経済学が有効だった時代は、第二次世界大戦後のインフラ整備、製造業主導の経済成長、そして若年人口が多かった社会だった。需要を刺激すれば供給が追いつき、雇用が生まれ、賃金が上がる――その前提があったからこそ成立していた理論だ。
だが現在の日本は、そんな単純な経済構造ではない。
・人口は減り続け、労働力は不足
・インフラはすでに整備され、むしろ老朽化対策に追われている
・高齢化が進み、消費性向の低い層が社会の大半を占める
この現実の中で、「財政出動で景気回復を」「需要喚起で物価を上げるべき」といった主張を続けるのは、まるで化石のような政策議論だ。いま必要なのは、現代の構造に合った政策であり、減税の評価もその文脈で行うべきである。
減税はインフレを生むのか? 答えはノー
「減税するとインフレが起きて国民が苦しむ」という言説がある。しかし、近代経済学の視点から見ると、この主張には根拠が薄い。
インフレにはいくつかの種類があるが、現在の日本が直面しているのは典型的なコストプッシュ型インフレである。エネルギー価格や輸入資源の高騰、為替変動による原材料価格の上昇など、供給側のコスト増加が物価を押し上げているのだ。
このような状況で、消費税やガソリン税を引き下げたとしても、それが「需要の爆発」を引き起こすとは考えにくい。むしろ、税負担を減らすことによって物価の上昇圧力が和らぐ可能性の方が高い。
近代経済学では、「物価上昇率がマイルドであれば望ましい」とされてはいるが、実質賃金が上がらない中でのインフレは“害悪”であると明確に区別されている。
減税は「正しく使えば」インフレ抑制にもなりうる
消費税減税やガソリン税の見直しは、家計にとって即効性のある支援策であり、物価の実質的な引き下げ効果が期待できる。
・消費税率が下がれば、商品やサービスの価格が実質的に下がる
・ガソリン税が減れば、物流コストが下がり、小売価格も下がる
これは「減税=インフレ促進」という短絡的な話とは真逆だ。
むしろ、“国が間接的に価格調整に関与する”という合理的な手段として、現代のインフレ対応策になり得る。
近代経済学では、税と価格の関係も市場メカニズムの一部として捉えられており、「価格調整のための税政策」は十分に整合的なアプローチである。
財政赤字論の“呪い”から解放されよ
減税反対論では、必ず「財政赤字が拡大する」と言われる。だが、それが即座に破綻を意味するというのは誤解である。
日本は、通貨発行権を持ち、自国通貨建てで国債を発行している。国債の利払いも円建てであり、財政危機に直結する国際的な要因(デフォルト、外貨準備不足)とは構造が異なる。
もちろん無限に支出して良いわけではない。だが、減税によって景気が改善し、税収が増えれば、「税率を下げても税収は増える」=ラッファー効果もあり得る。実際、日本では過去に法人税率を引き下げながら税収が増加した例もある。
近代経済学では、財政の健全性を“歳出対効果”と“長期的成長力”の中で評価すべきとされており、単なる赤字額だけを問題視するのは時代遅れだ。
「誰にとってのインフレか」を問え
インフレが悪なのではない。だが、「現状のインフレが誰を苦しめているか」という視点が抜け落ちた議論は無意味だ。
物価が上がっても、企業が価格に転嫁できて利益が出るなら良い。だが、その利益が内部留保に積み上がり、労働者に還元されなければ、庶民の実質所得は減るだけだ。
一方、減税で手元にお金が残れば、消費が活性化し、企業は設備投資や雇用に回しやすくなる。これこそが、現代的なインセンティブ設計の在り方ではないか。
減税を恐れるな、インフレに騙されるな
「減税をすればインフレが進み、財政も危うくなる」。
これは、過去の時代に通用した“古典的な恐怖論”にすぎない。
現代の経済はもっと複雑で、柔軟で、ダイナミックだ。
そして減税は、その経済の歯車を整え直す一つの手段になり得る。
ケインズ的な“政府主導・一律支出”ではなく、市場と家計に正しく働きかける減税政策こそが、持続可能な回復の第一歩だ。
時代に合わない理論に縛られることなく、現実を直視し、柔軟で合理的な経済政策を求めよう。
いま必要なのは、“安心して暮らせる経済”を取り戻すための、構造に即した減税である。