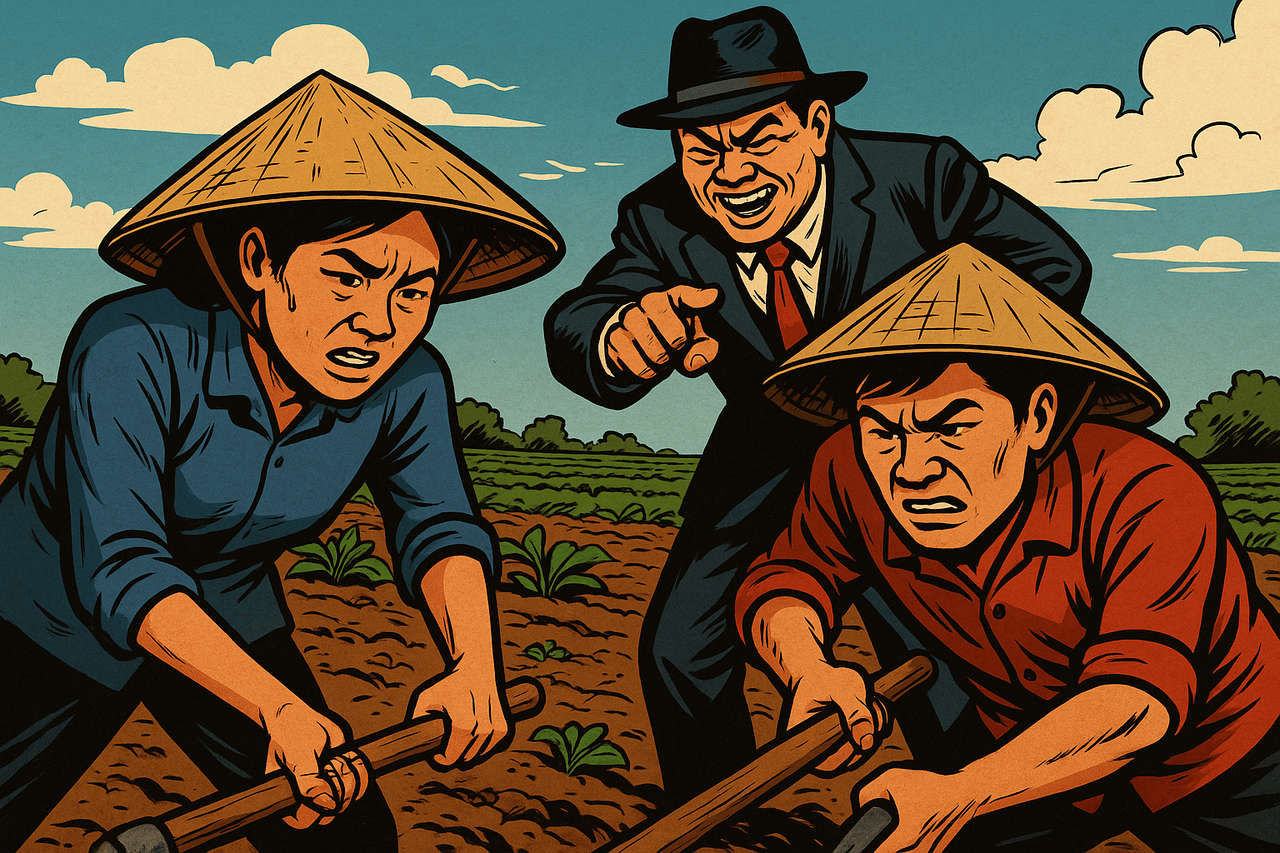労働力不足だけじゃない、「外国人の子ども」にも国費が流れる仕組み
2025年の夏、日本の人口構造に静かな変化が起きている。
出入国在留管理庁によれば、6月末時点の在留外国人数は395万6619人。昨年末から5.0%増え、過去最多を更新した。日本の総人口に占める割合は3.2%。単純計算すれば、年末には415万人に達する見込みだ。つまり、国民の約33人に1人が外国籍という時代が目前に迫っている。
増えているのは単なる短期労働者ではない。注目すべきは「特定技能2号」の急増だ。
これは、永住に近い形での就労・家族帯同を可能にする資格で、2024年12月時点でわずか832人だったが、2025年6月には3073人へと約3.7倍に膨らんだ。政府が打ち出した「人手不足解消策」は、実質的に“定住政策”へと変貌しつつある。
その影響は地方自治体の現場に直撃している。
地方の首長たちが声高に「外国人共生!」を叫ぶのは、労働力確保のためだけではない。そこには、交付金と財政の計算がある。
地方交付税は、自治体の住民票に基づく人口をもとに算定される。外国人も住民票を持てば「人口」としてカウントされる。つまり、外国人住民が増えれば地方交付税の算定額が増える可能性があるのだ。労働者であると同時に“財源を生む存在”でもある。
法務省の「外国人受入環境整備交付金」も見逃せない。多言語案内、相談窓口、通訳支援体制などの整備に対し、国から補助が出る。外国人が多いほど交付対象が増える仕組みで、自治体は「共生」を掲げるほど国費を受け取りやすくなる。さらに、外国人家庭が増え、子どもが生まれると「子ども・子育て支援交付金」に多言語対応加算がつき、1施設あたり年80万〜805万円が支給される。
つまり、外国人が増える→交付税が増える→外国人の子どもが増える→子育て交付金も増える──というサイクルが、静かに自治体の財政を潤している。
外国人増加が自治体にもたらす財政効果
| 外国人の増加要因 | 自治体にとってのメリット | 関連制度・補助金 | 補助額の目安 |
|---|---|---|---|
| 労働者・住民票登録者 | 地方交付税の算定人口に加算 | 地方交付税 | 人口に応じ増減 |
| 外国人向け窓口や多言語案内 | 体制整備の初期コストを国が補助 | 外国人受入環境整備交付金(法務省) | 人数に応じ変動 |
| 外国人家庭の子育て支援 | 多言語対応・ICT支援の加算 | 子ども・子育て支援交付金(内閣府) | 年80万〜805万円/箇所 |
この構造が自治体の行動を変えた。「外国人共生」はもはや理想ではなく、財源確保と人口維持のための“政策装置”になりつつある。
ある市の担当者はこう語る。
「外国人の住民登録が1000人増えると、単純計算で数千万円単位の交付税に影響します。共生事業をやらない理由がなくなるんですよ」
言葉の裏にあるのは、理念ではなく、現実だ。
この構造変化の背景にはもう一つの統計がある。厚生労働省の人口動態統計によれば、外国人の出生数が全体の3.1%を超えた。2024年、外国人の父母による出生は2万2738件に達し、過去最多。日本人の出生数が急減するなか、外国人出生だけが増加している。
日本人と外国人の出生数の推移(2013〜2024年)
| 年 | 外国人出生数(人) | 日本人出生数(人) | 外国人出生比率(%) |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 12,730 | 1,024,000 | 1.2 |
| 2014年 | 14,000 | 1,005,000 | 1.4 |
| 2016年 | 17,000 | 976,000 | 1.7 |
| 2018年 | 17,500 | 918,000 | 1.9 |
| 2019年 | 19,000 | 865,000 | 2.1 |
| 2021年 | 18,000 | 805,000 | 2.2 |
| 2022年 | 19,500 | 770,000 | 2.5 |
| 2023年 | 20,000 | 727,000 | 2.7 |
| 2024年 | 22,738 | 720,000 | 3.1 |
この表が示すのは、単なる統計ではない。
2013年に約1万2700人だった外国人出生が、わずか10年でほぼ倍増した一方、日本人出生は30万人以上減った。つまり、「増えているのは外国人の子どもだけ」という、構造的な人口置換が始まっている。
以前に作成したグラフ(外国人と日本人の出生推移を重ねたもの)でも、この傾向は明確だ。日本人出生が下り坂を描く中、外国人出生はゆるやかに上昇を続けている。
自治体が「共生」を掲げる背景には、この数字の現実がある。共生を進めるほど、補助金が入り、人口も「見かけ上」増える。地方創生と財源確保が、同じ文脈で語られる時代になった。
実際、宮崎県や横浜市などは「多文化共生」を地域ブランドに据え、国からの補助金と企業誘致の両面で成果を上げている。外国人向けの多言語窓口や文化教室が整備され、地域経済にも一定の波及効果を生んだ。だが一方で、「補助金で整備しても、維持費が地元負担になる」という不満の声も多い。
現場職員はこうこぼす。「共生の看板は立派でも、人を雇う予算はない。制度が短期で、支援員を継続雇用できない」。
国の支援が“導入補助”で止まっている現状が、制度の持続性を脅かしている。
政府の狙いは明確だ。外国人労働者の受け入れを進めたいが、中央で一元管理するコストは高い。
だから、「共生」という言葉で地方に負担を押し付ける。
法務省や内閣府は「環境整備交付金」という“飴”を与え、地方に実務を担わせる。これが日本の「分散型移民政策」の実態だ。
結局のところ、外国人共生は“理念”でありながら“財政戦略”でもある。人口減少に苦しむ地方にとって、外国人住民の増加は救いであり、同時に依存でもある。
だが、数字だけを追いかける政策は長続きしない。本来の共生とは、国籍を問わず、同じ地域の一員として暮らす仕組みを作ること。補助金で施設を整えることではなく、地域の人間関係を築くことだ。
外国人住民が増え、外国人の子どもが地域で育つ──その現実を、どう受け止めるか。「共生」を財源の言い換えにするのか、それとも地域の再生戦略に変えるのか。今問われているのは、政治の覚悟と地域の誠実さだ。
参考サイト
外国人の出生数3%超 新たな増加要因として浮上