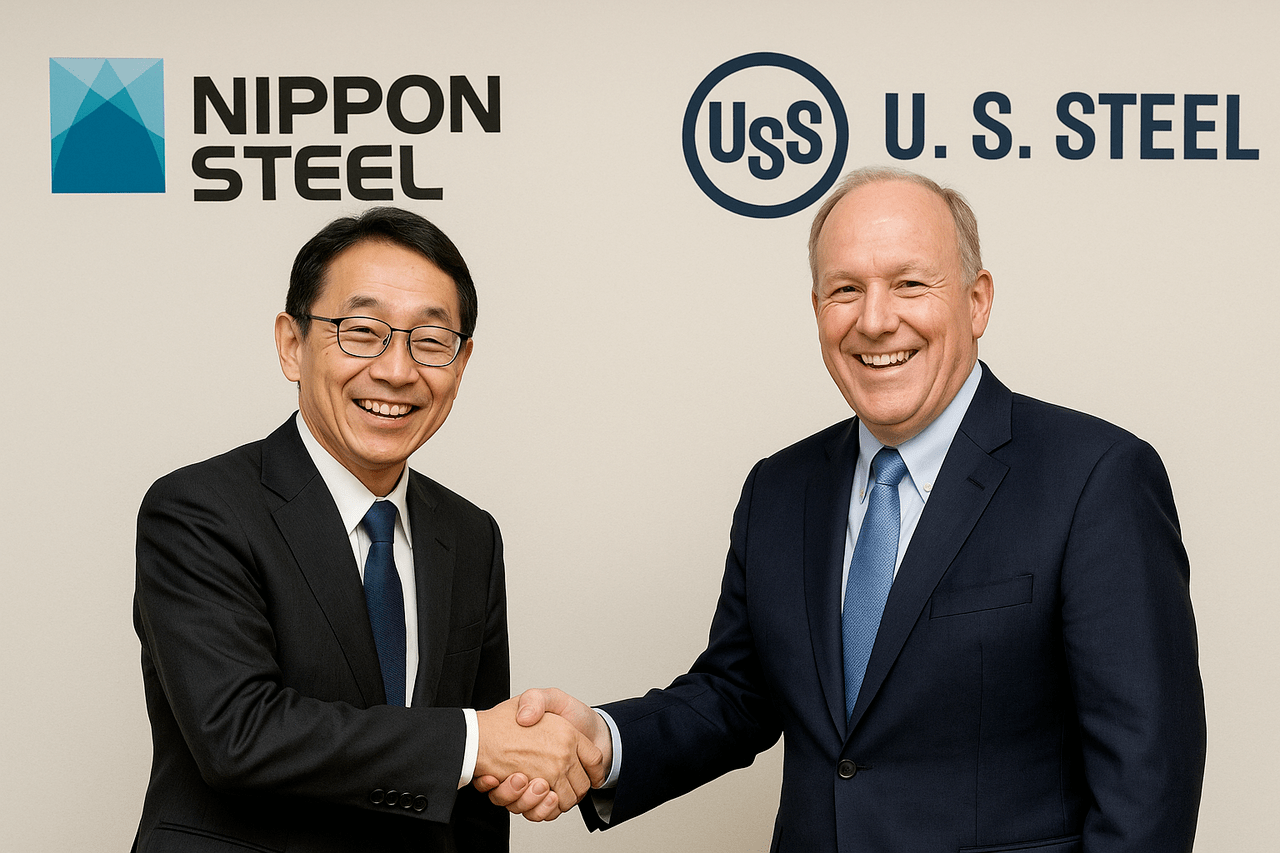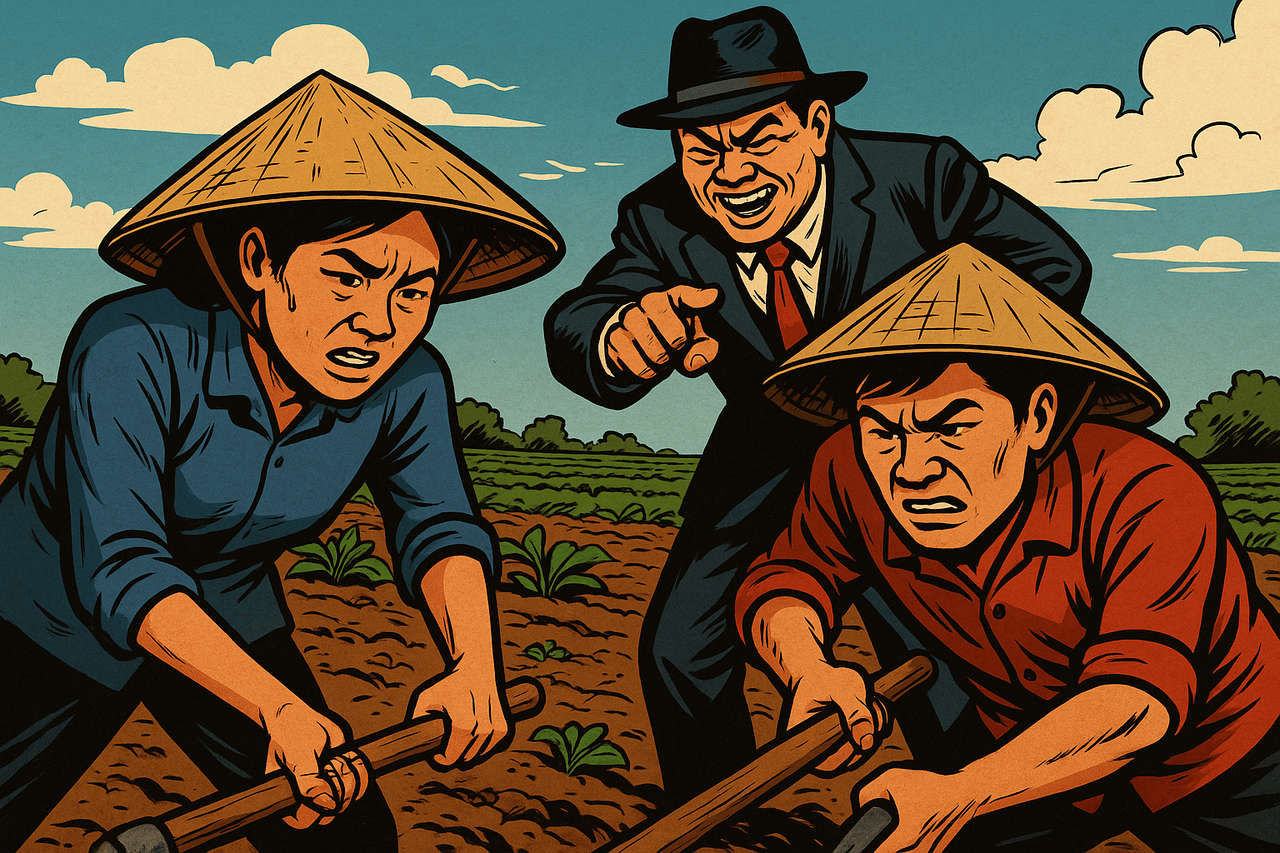長射程ミサイル運用、日本主体で発射 新設の統合司令部が指揮
- 2025/3/24
- 報道・ニュース

防衛省・自衛隊は、長射程ミサイルの運用に関して、日本側が主体的に発射を行い、米軍の支援に依存しない方針を策定した。この方針は、3月24日に発足する陸海空自衛隊の指揮を一元化する「統合作戦司令部」が中心となり、運用される。
長射程ミサイルの重要性
長射程ミサイルは、通常より遠方のおおむね1,000キロ以上の距離を攻撃可能な「スタンドオフミサイル」として位置付けられ、敵の攻撃圏外からの攻撃手段として有効である。また、敵領域内の軍事目標を攻撃する「反撃能力」としても活用され、防衛力強化の要とされている。
運用体制と課題
長射程ミサイルの運用には、人工衛星や無人機、レーダーなどの多様な情報収集手段による探知・追尾が必要であり、地上発射型だけでなく、艦艇や戦闘機など多様な発射手段を持つことで抑止力を発揮する。そのため、陸海空自衛隊を一体運用する必要があり、新たに発足する統合作戦司令部の一元指揮が前提となる。
しかし、長射程ミサイルの運用を日本主体で行うためには、いくつかの課題が残されている。まず、2027年度に先行配備する予定の米国製巡航ミサイル「トマホーク」の運用には、互換性のあるシステムを持つ米軍の支援が不可欠である。また、主軸となる国産巡航ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」の一元運用に必要な「統合指揮ソフトウェア」などの整備には、2029年度までの期間を要する見込みである。
米国との協力と情報共有の重要性
日本が長射程ミサイルを独自に運用する方針を進める中で、米国との協力関係の維持は重要な課題である。自衛隊幹部は、「米側が許可しないと発射できない事態にしてはいけない」と述べ、情報共有や運用面での協力体制の構築が必要であることを指摘している。
統合作戦司令部の役割
3月24日に発足する統合作戦司令部は、陸海空自衛隊の指揮を一元化し、長射程ミサイルを含む各種兵器の効果的な運用を目指す。これにより、迅速かつ柔軟な対応が可能となり、抑止力の強化が期待される。
日本が長射程ミサイルの運用を自国主体で行う方針は、防衛力強化の一環として重要な意義を持つ。今後は、米国との協力関係を維持しつつ、必要なシステムや体制の整備を進め、効果的な運用を実現していくことが求められる。