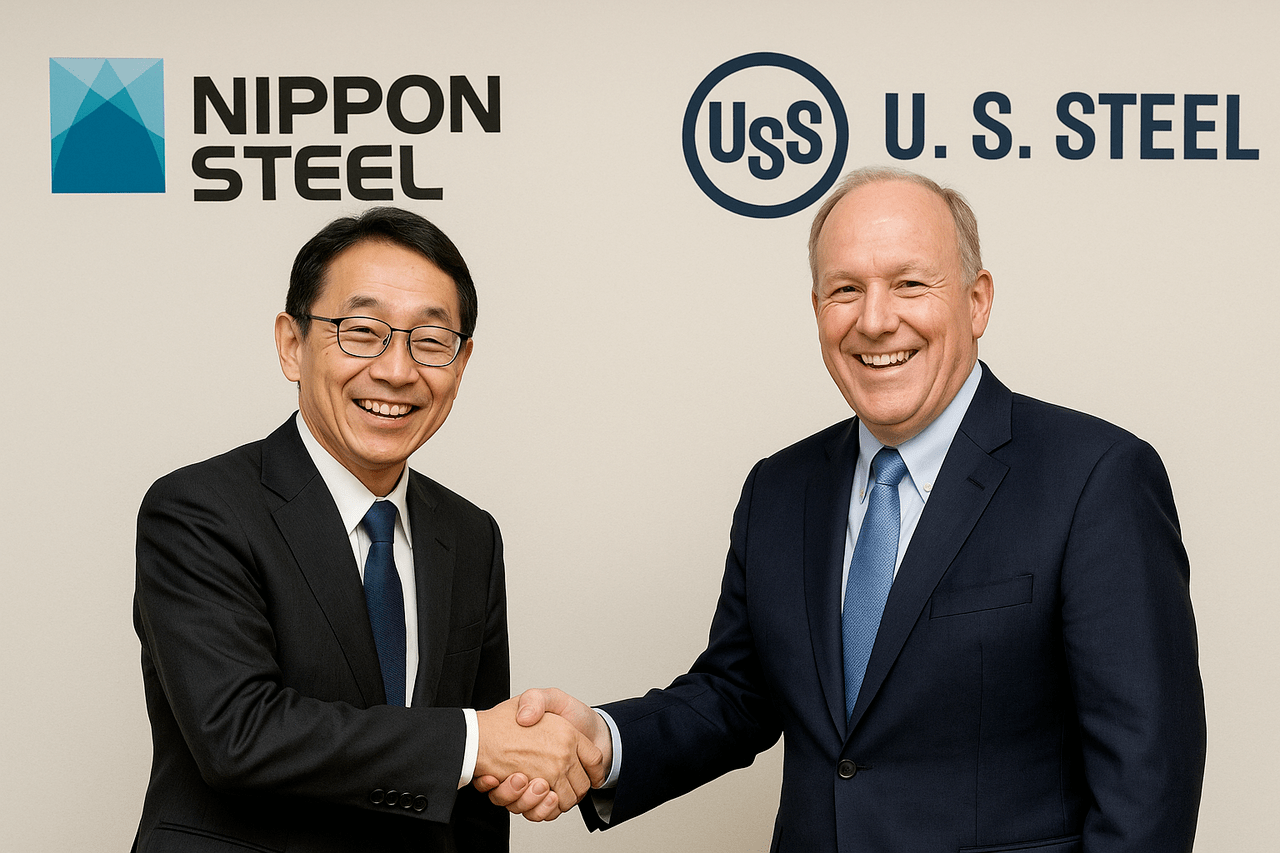第217回国会における石破内閣総理大臣施政方針演説の内容
- 2025/1/25
- 記事
石破内閣総理大臣の施政方針演説は、今後の日本に向けた多くの課題とその解決策を示唆する重要な内容が盛り込まれています。この演説は、日本の未来を築くためのビジョンとして、国づくりの基本軸や地方創生、経済政策に至るまで、広範囲にわたる施策を提案しています。しかし、その中には実行の難しさや、実際に効果を上げるための工夫が求められる部分もあります。今回は、石破総理が示した「楽しい日本」実現に向けた施策の内容と、その背後にある課題について掘り下げて考察してみたいと思います。
国づくりの基本軸
解説
石破総理は、日本の現状として生産年齢人口の減少と人材不足に触れ、それに対応するために「人財尊重社会」の構築を掲げています。特に「人材希少社会」に突入した現在、すべての人々の幸福実現を目指す社会づくりが重要だとし、その中で自立と持続可能性が重視されるべきだと述べています。また、堺屋太一氏の著書を引用し、「強い日本」から「楽しい日本」への転換を提唱しています。ここで「楽しい日本」とは、個人が自己実現を図り、多様な価値観を尊重する社会を指します。
問題点
このビジョン自体は魅力的ですが、具体的にどのように実現するのかが不明瞭です。特に「楽しい日本」の実現には、教育改革、労働市場改革、社会保障制度の改革など、多方面にわたる施策が必要ですが、それらがどのように連携し、実行に移されるかは不透明です。人口減少という厳しい現実に対して、どれだけ迅速に適応できるかが今後の課題です。
地方創生2.0、「令和の日本列島改造」の具体化
解説
地方創生2.0は、田中角栄元首相の「日本列島改造」を現代的に再構築するもので、都市と地方のバランスの取れた発展を目指しています。都市と地方の間で人々が移動しやすい環境を整備し、特に若者や女性の地方定着を支援します。また、リモートワークの普及や企業の地方移転、地方大学の強化といった施策を通じて、地方経済の活性化を図ります。
問題点
地方創生の成否は、地域ごとの独自性を活かした政策がどれだけ実効性を持つかにかかっていますが、地域の特性を無視した均一的な施策では効果が限られます。特に、企業の地方移転や若者・女性の地方定着を促進するためには、生活環境や地域の雇用の質を根本的に改善する必要があります。また、移住後のサポート体制が不十分な場合、定着率が低くなる可能性があります。
経済・財政・社会保障
解説
石破総理は、賃上げを成長戦略の核と位置づけ、物価上昇に対応した賃上げの実現を目指します。最低賃金を引き上げ、労働市場改革を進めるとともに、企業が賃上げを行いやすい環境を整備します。また、資産運用立国を掲げ、個人資産の形成を支援する政策も導入しています。さらに、地域経済や中小企業の支援を強化し、経済全体の活力向上を目指しています。
問題点
賃上げが進む一方で、企業の負担増加をどのように抑制するかが課題です。特に、中小企業に対しては、賃上げを実現するための支援が必要ですが、それをどれだけ効果的に提供できるかが鍵となります。また、資産運用立国のビジョンには、低所得者層への配慮が不足していると指摘される可能性があります。資産運用を進める一方で、貧困層の生活支援や格差是正策が不十分だと、経済的な不平等が拡大する恐れがあります。
新時代のインフラ整備
解説
総理は、脱炭素社会を実現するための再生可能エネルギーの拡充や水素燃料の供給拠点の整備、デジタル・トランスフォーメーション(DX)を支えるインフラ整備を進めるとしています。特にAIや半導体分野への投資を呼び込み、産業拠点の再配置を促進することで、競争力の向上を目指しています。
問題点
再生可能エネルギーや水素エネルギーへの移行は重要ですが、その実現には膨大な投資と技術的な課題が伴います。特に、エネルギーの安定供給とコスト面での調整が難しく、社会全体での合意形成が必要です。また、AIや半導体分野の投資促進に関しては、労働力の再教育や産業転換が必要であり、それに伴う社会的コストが問題となる可能性があります。
広域リージョン連携
解説
都道府県を超えた広域連携を推進することで、自治体間での協力を強化し、効率的な政策実施を目指します。これにより、地域ごとの課題解決に向けた柔軟な対応が可能になるとしています。
問題点
広域連携を進めるには、自治体ごとの利害調整や意見の相違をどう乗り越えるかが課題です。また、地域間での格差が生じる可能性があり、一部の地域に利益が偏ると、全体のバランスが崩れる恐れがあります。
1 国づくりの基本軸
今年は戦後80年、そして昭和の元号で100年に当たる節目の年です。これまでの日本の歩みを振り返り、これからの新しい日本を考える年にいたしてまいります。
そのためには、我が国の直面する現実を直視しなければなりません。
我が国の生産年齢人口は、これからの20年で1500万人弱、2割以上が減少すると見込まれております。このような中、かつて人口増加期に作り上げられた経済社会システムを検証し、中長期的に信頼される持続可能なシステムへと転換していくことが求められております。
今や、我が国は「人材希少社会」に入っています。年齢や障害の有無にかかわらず希少な人材を大事にする社会づくり、すなわち、国民一人一人の幸福実現を可能にする、人中心の国づくりを進め、すべての人が幸せを実感できる、人を財産として尊重する「人財尊重社会」を築いていく必要があります。
加えて、食料自給力、エネルギー自給率が低い現状では、外的な事象に国民生活が大きく影響を受けてしまう懸念があります。より自立した形で国民生活を守ることができるよう、戦略的な国家運営が必要です。
新しい日本を創る上で、「サステナブル」で「インディペンデント」であること、すなわち持続可能で自立することを重視しなければなりません。そのため、価値観の転換が必要だと考えております。
故・堺屋太一先生の著書によれば、我が国は、明治維新の中央集権国家体制において「強い日本」を目指し、戦後の復興や高度経済成長の下で「豊かな日本」を目指しました。そして、これからは「楽しい日本」を目指すべきだと述べられております。
私はこの考え方に共感するところであり、かつて国家が主導した「強い日本」、企業が主導した「豊かな日本」、加えてこれからは一人一人が主導する「楽しい日本」を目指していきたいと考えております。
「楽しい日本」とは、すべての人が安心と安全を感じ、自分の夢に挑戦し、「今日より明日はよくなる」と実感できる。多様な価値観を持つ一人一人が、互いに尊重し合い、自己実現を図っていける。そうした活力ある国家です。
外交・安全保障体制、防災立国、感染症対策など危機管理を確立し、賃上げと投資が牽(けん)引する成長型経済を実現するとともに、人財尊重を基軸として、楽しさを実現できる、バランスの取れた国づくりを目指します。2 地方創生2.0、「令和の日本列島改造」の具体化
(「令和の日本列島改造」)
「楽しい日本」を実現するための政策の核心は、「地方創生2.0」です。これを、「令和の日本列島改造」として強力に進めます。
都市対地方という二項対立ではなく、都市に魅力を感じる方、地方に魅力を感じる方、そうしたお一人お一人の多様な幸福が実現できる場として、都市も地方もその魅力を高めていきます。
かつて、田中角栄元首相の「日本列島改造」では、道路や鉄道といったハードなインフラの整備を起点として人の流れを生み出し、国土の均衡ある発展が目指されました。
「地方創生2.0」は、官民が連携して地域の拠点をつくり、地域の持つ潜在力を最大限引き出し、ハードだけではないソフトの魅力が新たな人の流れを生み出す。新技術を徹底的に活用し、一極集中を是正し、多極分散型の多様な経済社会を構築していくものです。
「令和の日本列島改造」は、5本の柱で、厳しい国際競争の中、日本全体の活力を取り戻すべく進めてまいります。(若者や女性にも選ばれる地方)
第1の柱は、「若者や女性にも選ばれる地方」であります。若者や女性が「楽しい」と思えるような新しい出会いや気づき、そこから生まれる夢や可能性が重要です。
新たな人の流れを太くするため、いわゆる関係人口に着目し、都市と地方といった二地域を拠点とする活動を支援します。地域に継続的に関わる方々が登録でき、地域づくり活動に参加する担い手となっていただける「ふるさと住民登録制度」等の有効性について検討を行い、結論を得てまいります。地域の外の方々がリモートワーク等で地方の取組を応援しやすい環境を作ります。
若者や女性が働きやすく魅力ある職場づくりを進めるため、アンコンシャス・バイアス、すなわち無意識の思い込みの解消を図るとともに、男女の賃金格差の是正を促進する法案を提出いたします。車座対話の開催や地域に対するサポートを進めることにより、日本全体の機運を高め、取組の裾野を広げてまいります。
日本各地で事業を起こそうと考えている若者や女性の方々の声を伺い、起業の障害を解決し、ネットワークの構築を支援する等の取組を強化します。
日本全国に約9000社存在する中堅企業や成長志向の中小企業は、地方経済を支える存在です。こうした企業の賃上げを伴う成長投資を強力に支援し、全都道府県での地方版政労使会議の開催等により、最低賃金を含め、地方で賃金が上がっていく環境を創り出してまいります。
暮らしやすいまちづくりには、官民で、AI(人工知能)・デジタル技術を活用し、地方の持続可能な生活インフラを作っていくことが重要であります。自動運転の実装加速に向けた制度整備を進めるとともに、電子カルテ等の医療機関での共有、遠方の医療機関まで行かずともオンラインで適切な診療を受けられる体制の整備を進めます。
人口減少下においては、官民が連携した人づくりや公教育の再生・改革により、一人一人が持つ可能性を最大限引き出すことが必要です。そのために大事なことは、教育の内容と質であり、こどもたちをどのように育てたいのかを明確にすることです。知識や能力だけでなく、歴史や文化、地域や周りの人々を大切にし、行動する力を有した人材や、大学や農業・工業高校等における観光等の地域の魅力やニーズを捉えた産業やサービスを支える人材を育成します。教職員の働き方改革や給与面を含む処遇改善等を進めてまいります。
これらの取組を応援するため、地方公務員の兼業・副業の弾力化、会計年度任用職員の在り方の見直し等により、地域の中の方々が力を発揮できる環境を整備します。国の職員が、課題を抱える市町村に寄り添って、顔が見え、熱が伝わる伴走支援を行う仕組みを新たに始めます。(産官学の地方移転と創生)
第2の柱は、「産官学の地方移転と創生」です。
まずは、官が一歩前に出ます。防災庁など政府関係機関の地方移転、国内最適立地を推進します。これまでの取組を検証し、地方からの提案を改めて募り、日本全体にとって望ましい効果を生み出すのはどこかという視点を踏まえ、順次結論を出してまいります。
「地方創生2.0」では民の力をいかすことが不可欠です。地方創生に取り組む経営者や現場の方々との意見交換を重ね、都市部に立地する企業の本社機能の移転などを実現する環境整備を進めます。
地方でも地域の中核となる特色ある地方大学が育ちつつあります。東京23区内の大学等の定員の抑制を行いつつ、地方大学による実践的な人材の育成を進めます。(地方イノベーション創生構想)
第3の柱は、「地方イノベーション創生構想」です。地方創生1.0では、優良事例が点の取組で終わり、相互に作用し合い面的な広がりにつながる化学変化が起きませんでした。その反省を踏まえ、地方における新結合を通じた新たな産業分野の創造やイノベーションの開花を目指します。
大学・企業・自治体等が連携し、地域にイノベーションの主役を生み出し、地域活性化や社会課題解決を実現するスタートアップとして大きく育てていける環境を整備します。スタートアップ育成5か年計画を強化し、地域における拠点都市の拡充や自治体による調達の促進など、独自性ある取組を大胆に支援いたします。
グローバル、あるいはローカルな様々な社会課題が、その解決に向けたイノベーション、革新的な製品・サービス、新たな市場を生み出す可能性を秘めております。大学や研究機関等の産学連携拠点に対する支援を抜本的に強化いたします。
世界有数の潜在力を持つ日本の農林水産業・食品産業を、徹底的な高付加価値化により、基幹産業として確立します。これらが儲(もう)かる産業となるよう、スマート化・大区画化など生産基盤を強化します。米を世界へ輸出するプロジェクトの推進、安定的な輸出入と備蓄の確保などを通じて、食料安全保障を確保します。総合的な林業・木材産業施策として、施業地の集積・集約化やCLT等の技術開発・普及など、森林資源の循環利用を進めます。水産業の発展のため、水産資源管理を行いつつ、スマート化や海業の全国展開を進めます。
新たな重点として、官民連携により文化芸術・スポーツの振興を図ります。その効果的な広報等により地方創生に繋(つな)がる観光産業の活性化を進めます。海外売上げで半導体や鉄鋼に肩を並べるエンタメ・コンテンツ産業について、2033年までに海外売上高を5兆円から20兆円とする目標を掲げ海外展開を支援し、クリエイターの方々の育成や安心して働ける環境の整備を含めその発展を強力に支援します。
今年はいよいよ大阪・関西万博が開催されます。明日の世界を担うこどもたちに、未来社会への希望を持って、将来について考える機会となることを願って止(や)みません。開催国である日本そして各地域が世界との交流を深め、自らの魅力を世界に向けて発信する絶好の機会となるよう、政府として最大限の力を尽くします。多くの方々に御来場いただき、各地を訪ねていただいて、万博と地方創生のシナジー効果を実現します。(新時代のインフラ整備)
第4の柱は、「新時代のインフラ整備」です。GX(グリーン・トランスフォーメーション)、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を支える「新時代のインフラ」を軸として、産業拠点や生活拠点の再配置を促進します。
再生可能エネルギーや原子力といった脱炭素電源、そして水素等の次世代燃料供給拠点を拡大するとともに、その供給網を効率的に整備していきます。脱炭素電源の整備と新たな産業用地や関連インフラの整備を共に促す施策を具体化します。150兆円超のGX投資を呼び込むための成長志向型カーボンプライシングの制度化及び循環経済への移行に向けた法案を提出いたします。
AIは、今や、国の競争力や社会の豊かさを左右する極めて重要な技術です。イノベーションの加速とリスクへの対応を両立させる法案を提出いたします。AI、データセンター等を繋ぐ情報通信ネットワークを、サイバーセキュリティを確保しつつ整備いたしてまいります。AI・半導体分野に50兆円を超える投資を引き出す環境整備のための法案を提出します。(広域リージョン連携)
第5の柱として、都道府県域を超えた広域連携の新たな枠組みである「広域リージョン連携」を強力に推進します。
自治体が、他の自治体との縦横のつながりを最大限いかせる最適な体制を築きます。必要な制度改革を進め、自治体同士の広域連携を抜本的に強化します。3 経済・財政・社会保障
(物価上昇に負けない賃上げ、資産運用立国)
「人財尊重社会」における経済政策にとって、最重視すべきは賃上げであります。「賃上げこそが成長戦略の要」との認識の下、物価上昇に負けない賃上げを起点として、国民の皆様の所得と経済全体の生産性の向上を図ってまいります。
33年ぶりの高水準の賃上げとなった昨年の勢いで、大幅な賃上げを促すとともに、最低賃金を着実に引き上げ、2020年代に全国平均1500円という高い目標に向かってたゆまぬ努力を続けることにより、賃金は据置きで動かないという縮み志向を過去のものといたします。
賃上げができるよう、多くの中小企業に利益を上げていただくためには、取引の上流から下流まで、適切な価格転嫁や生産性向上を実現することが重要です。下請法の改正法案を提出するとともに、自治体等の官公需での価格転嫁を促進します。
賃上げの原資となる生産性の向上への支援を強化するため、各業種の実態に即した省力化投資を進めるための計画を策定し、現場での支援体制を整備します。
人材・経営基盤を強化する事業承継やM&Aを後押ししてまいります。望まない非正規雇用を減らし、同一労働同一賃金を実現するとともに、リ・スキリング、ジョブ型人事、労働移動の円滑化の三位一体の労働市場改革を強力に進めます。求職者の状況に応じたきめ細かい就労支援を行います。
現在や将来の賃金の増加等をいかした資産形成の後押しも重要であり、NISAやiDeCoの充実など資産運用立国の取組を強化します。
賃上げの効果が出るまでの間にも物価高対策を講じます。地域の実情に応じて、エネルギーや食料品価格の高騰に苦しむ方々、価格転嫁が困難な中小企業、学校給食費への支援等を行う重点支援地方交付金や、低所得者世帯の方々に対する給付金など総合経済対策で決定した施策を迅速に執行してまいります。(日本経済の活力向上、投資立国)
日本のGDPは、1994年には世界の18%を占めていましたが、直近の2023年では4%となっています。「今日より明日はよくなる」と実感できる「楽しい日本」となるには、こうした流れを転換し、持続的な成長が必要です。このため、コストカット型経済から高付加価値創出型経済への移行、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していきます。官民投資フォーラムを開催し、国内投資目標を示し、規制改革の検討を深め、大胆な国内投資促進策を具体化することを通じ、投資立国の取組を強化します。
科学技術・イノベーション基本計画の改定を進め、AI、量子、バイオ、宇宙、フュージョン等の戦略分野での投資を促してまいります。
企業が未来に向けた成長投資に更に踏み込むための会社法改正に向けた具体的議論を開始します。長期の企業価値向上に向けた投資家との対話等を通じて、人や技術への投資を進める環境を整えます。(経済安全保障)
経済安全保障の観点から、我が国の自律性と不可欠性を高めるため、重要サプライチェーンの国内回帰・立地促進を含む強靱(きょうじん)化や技術流出対策等の取組を進めます。官民が連携し脅威・リスクを分析する経済インテリジェンス機能の強化を図ります。
国、重要インフラ等に対するサイバー攻撃を排除するため、能動的サイバー防御を可能とする法案を提出いたします。(財政の健全化)
「経済あっての財政」の考え方の下、成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳出・歳入両面の改革を継続し、引き続き財政健全化を目指します。金利のある世界となる中、大災害や有事に備えた財政余力を確保する観点も踏まえ、経済・財政新生計画の枠組みの下、今年の骨太方針において、早期のプライマリーバランス黒字化実現を含め、今後の財政健全化に向けた取組を示します。(社会保障)
社会保険料は安心のための拠出であり、すべて必要な給付として再分配されます。国民所得に対するその割合は、コロナ禍以前の水準に低下しております。一方で、少子高齢化に対する将来不安があるため、社会保障制度への不安が解消いたしません。年齢にかかわらず適切に支え合うことを目指す全世代型社会保障の理念に則り、改革工程に沿って着実に進めます。高額療養費制度の見直しなどにより、保険料負担の抑制につなげます。
来年度、少子化対策は本格実施の年を迎えます。父母がともに育児休業を取得した際の給付率を手取りで10割に引き上げるとともに、保育士等の配置・処遇を改善します。
コロナ禍の検証を踏まえた万全の感染症対策の実施に加え、入院だけでなく、外来・在宅医療や介護との連携も含む新しい地域医療構想を策定し、地域での協議を促進します。あわせて、医師偏在対策を総合的に推進するための法案を提出いたします。
年金制度の財政状況は、支え手の増加などにより前回の見直し時に比べ好転しております。今後とも成長型経済の実現に努めるとともに、働き方に中立的な制度とするなど、将来にわたる安心をより確実なものとしてまいります。
単身の高齢者が増加する中、介護体制の整備とともに、生活に困難を抱える方、障害のある方、子育て世帯が、地域の中でつながり、支え合い、共に地域を創っていく地域共生社会の実現を目指します。
旧優生保護法を執行してきた立場として、真摯な反省に立ち、補償金の着実な支給と差別のない社会の実現に力を尽くしてまいります。
令和7年秋に日本で初めて開催される東京2025デフリンピックを強力に支援します。4 防災・治安
(防災・復興)
能登半島地震から1年、復興中の奥能登を襲った豪雨から4か月が経過しました。復旧・復興への着実な取組により、地震に係る応急仮設住宅は全て完成し、農林水産業や輪島塗の再開も進みつつあります。能登の賑(にぎ)わいと笑顔を一日も早く取り戻すため、災害廃棄物処理の加速、公営住宅の建設等により被災者の生活・生業の再建を強力に支援します。
「福島の復興なくして、東北の復興なし。東北の復興なくして、日本の再生なし。」引き続き、復興庁が司令塔となり、被災者の生活や産業・生業の再建、福島イノベーション・コースト構想の推進等に取り組みます。
阪神淡路大震災から30年が経ちました。その経験・教訓を忘れることなく継承し、災害対策にいかしてまいります。
我が国は、世界有数の災害発生国であり、平時の備えにより被害の最小化を図るとともに、発生時にはスフィア基準を踏まえた環境を迅速に提供する必要があります。こうした国家の責務を果たすため、災害対策基本法等の改正案を提出し、被災地での福祉支援やボランティアとの連携を推進します。豪雨等の災害の発生予測を高度化し、情報発信を強化します。
防災対応の司令塔として防災監を内閣府に設置するとともに、内閣府防災担当の機能を予算・人員の側面から抜本的に強化します。その上で、防災庁を令和8年度中に設置すべく、準備を加速します。
今後30年以内に、首都直下地震は70%程度、南海トラフ地震は80%程度の確率で発生するとされております。被災の地域や規模が予想できる大規模災害に対しては、自治体間の支援・受援の組合せの事前決定、支援物資の計画的備蓄など、事前防災を一層具体化いたしてまいります。
防災・減災、国土強靱化を着実に推進します。令和8年度からの実施中期計画については、施策の評価や資材価格の高騰等を勘案し、概ね15兆円程度の事業規模で実施中の5か年加速化対策を上回る水準が適切との考え方に立ち、本年6月を目途に策定します。人命・人権最優先の防災立国を構築し、世界一の防災大国にいたしてまいります。災害対策の知恵や技術を海外に発信し、世界の防災に貢献するとともに、新たな産業の柱にいたします。(治安)
犯罪は長期的に減少傾向にありますが、多くの国民が治安の悪化を感じています。「闇バイト」による強盗・詐欺、巧妙なサイバー犯罪等が後を絶たず、女性が悪質ホストクラブに搾取される問題も生じています。犯罪対策を強力に推進し、「世界一安全な日本」を実現します。
匿名・流動型犯罪グループに対し、仮装身分捜査等により検挙を徹底いたします。「闇バイト」の求人情報の削除の促進、SNS等での若者向けの注意喚起、防犯カメラの整備の支援等を進めます。
学校と連携したサイバー防犯指導、官民連携でのサイバー攻撃対処訓練等を推進します。また、悪質ホストクラブへの規制を強化する法案を提出するとともに、性暴力、DV、虐待等を防ぎ、被害者支援を推進します。5 外交・安全保障
間もなく4年目を迎えるロシアによるウクライナ侵略。我が国周辺での中国・ロシアの軍事活動の活発化。北朝鮮による核・ミサイル開発。戦後最も厳しく複雑な安全保障環境において、我が国の独立と平和、人々の暮らしを守り抜くためには、バランス・オブ・パワーに常に最大限の注意を払い、我が国自身の能力を高める、日米同盟を更なる高みに引き上げる、同志国との連携を更に拡大・深化する、こうした取組を進めなければなりません。同時に、彼我の誤解・誤算を避けるために、関係国との緊密な意思疎通を重ねることが死活的に重要であります。
防衛力は我が国の安全保障の最終的な担保です。我が国への侵攻に自らが主たる責任をもって阻止・排除する能力を保有し、もって我が国への侵攻自体を抑止することを主眼に、国家安全保障戦略等に基づき、防衛力の抜本的強化を着実に進めます。シェルターの確保等を着実かつ早急に進めるなど、国民保護の取組を強化します。
自衛隊の人的基盤の強化に取り組みます。自衛官が十分に充足されていないことは極めて深刻な課題であります。30を超える手当等の新設・金額の引上げなど過去に例のない取組を令和7年度から実現します。自衛官の処遇の魅力向上、若くして定年退職を迎える自衛官が退職後も活躍できる環境の創出等を内容とする法案を提出いたします。
基地負担の軽減、駐留に伴う諸課題の解決に引き続き取り組みます。昨年末、大浦湾側の地盤改良工事に着手することで、普天間飛行場全面返還の実現に向け大きく前進をいたしました。引き続き、着実に工事を進めてまいります。また、沖縄振興の経済効果を十分に域内に波及させ、それを実感していただくため、地元事業者の成長や県産品の活用に配意し、沖縄経済の構造改革に向けて支援を継続いたします。
日米同盟は我が国の外交・安全保障政策の基軸です。地域におけるパワーバランスが歴史的変化を遂げる中、力の空白が地域の不安定化につながることのないよう、日米の協力を更に具体的に深化させ、合衆国の地域へのコミットメントを引き続き確保しなければなりません。
また、日米豪印、日米韓、日米比を含め、地域における安全保障の重層的なネットワークを構築し、自由で開かれたインド太平洋を強化する上では、日米のリーダーシップは不可欠です。その際、我が国は同盟国として責任を共有し、応分の役割を果たさなければなりません。
来るべき日米首脳会談におきましては、トランプ大統領との間で、こうした安全保障や経済の諸課題につき、認識の共有を図り、一層の協力を確認し、日米同盟を更なる高みに引き上げたいと考えます。
韓国は国際社会の諸課題にパートナーとして協力すべき重要な隣国です。内政上の動きはありますが、現下の戦略環境の下、日韓関係の重要性は変わりません。韓国側とは、引き続き、国交正常化60周年を含め、緊密に意思疎通してまいります。
年頭にはマレーシア及びインドネシアを訪問し、先日はラオス首相をお迎えをいたしました。国際社会が対立と分断を深める中、ASEAN諸国との関係強化は、我が国のグローバル・サウス外交の観点からも、最優先事項の一つです。今後とも、海洋安全保障、災害対応、脱炭素化等につき実務的な協力を進めてまいります。
対ウクライナ支援、対露制裁を今後とも強力に推し進めます。
中国との関係では、懸案や意見の相違につき、主張すべきことは主張する、その上で、協力できる分野では協力していく、そうした現実的な外交を行ってまいります。価値を共有する同盟国・同志国との確固たる連携を大前提とした上で、中国の安定的発展が地域全体の利益となるよう、習近平主席とも確認した、「戦略的互恵関係」の包括的推進、「建設的かつ安定的な関係」の構築という大きな方向性に基づき、今後も首脳間を含むあらゆるレベルで中国との意思疎通を図ってまいります。日中韓の枠組みも前進させます。
日露関係は厳しい状況にありますが、我が国としては、領土問題を解決し、平和条約を締結するとの方針を堅持いたします。
拉致問題は、単なる誘拐事件ではなく、その本質は国家主権の侵害であります。拉致被害者や御家族が御高齢となる中で、時間的制約のある、ひとときもゆるがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題であります。日朝平壌宣言の原点に立ち返り、すべての拉致被害者の一日も早い御帰国、北朝鮮との諸問題の解決に向け、断固たる決意の下、総力を挙げて取り組んでまいります。
気候変動、軍縮不拡散といった地球規模の課題、各地の人道状況にも、引き続き正面から取り組みます。ガザ傷病者への医療支援を早期に実現すべく、関係国等との調整を進めてまいります。
私は、年頭の外国訪問において、LNG(液化天然ガス)の安定供給に向けた協力、脱炭素化に向けたアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)を通じた連携を確認いたしました。資源外交を引き続き強力に推進します。6 政治改革
戦後80年は民主主義を考える年でもあります。政治改革の課題について結論を得るのは我々政治家の使命であり、民主主義をどのように支えるかについての議論が重要です。国費による助成、企業団体や個人からの資金、そして政治家本人からの支出、それらのバランスはどうあるべきか。国費による助成を受け、原則として非課税であるという特別な扱いを受ける以上、それにふさわしい政党や政治団体としての規律の在り方をどのように考え、また、その規律をどのように担保していくか。そのための法制度の在り方も含めて、与野党の枠を超えて議論を深めていきたいと考えます。
民主主義の根幹である選挙についても、課題があります。
選挙活動について、これまで想定されなかったことが起き始めており、それらを踏まえた議論も求められています。民主主義は、多くの意見が健全な言論の場において戦わされてこそ成り立つものであり、それが担保される必要があります。
政治資金にしても、選挙活動にしても、重要なことは、有権者に判断材料が正しく提供されることであり、そうした正しい判断材料に基づいて、より幅広い世代のより多くの民意が政治に適切に反映されることです。それが国民主権の本質であり、今の選挙制度がそれにふさわしいものなのか、約30年の歴史を踏まえ、改めて党派を超えた検証を行い、あるべき選挙制度を議論していきたいと考えます。7 憲法改正等
今年は戦後80年の節目の年となります。国民の意識や国際情勢の変化を踏まえ、国のかたちを定める憲法のあるべき姿について、主権者である国民の皆様に案を示すのは、我々国会議員の責務です。国会による発議の実現に向け、今後、衆議院及び参議院に設置された憲法審査会において建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待いたします。
皇位の安定的な継承等は極めて重要であり、とりわけ皇族数の確保は喫緊の課題です。国会において、早期に「立法府の総意」が取りまとめられるよう、積極的な議論が行われることを期待します。8 結語
昨年の所信表明演説に引き続き、本施政方針演説におきましても、石橋湛山(たんざん)元首相の言葉を引いて、結びとしたいと存じます。石橋湛山元首相は、昭和32年の演説会で国会の運営の正常化、政界及び官界の綱紀粛正、雇用の拡大と生産の増加、福祉国家の建設、世界平和の確立という「五つの誓い」を述べられました。その第一である国会の運営の正常化については、自ら「反省すべき点は十分に反省するが、同時に反対党その他の協力を求め、国会がまっすぐに行くように」したいと表明されました。
第217回国会における石破内閣総理大臣施政方針演説
昨年の総選挙の結果、約30年ぶりの少数与党となりましたが、比較第一党として、自由民主党は、公明党とともに、今の、そして次の世代の国民の皆様に対して責任を持つ、責任与党でなければなりません。
党派を超えた合意形成を図るため、臨時国会に続き、与党、野党ともに、責任ある立場で熟議し、国民の納得と共感を得られるよう努めることが必要であります。
多様な国民の声を反映した真摯な政策協議によって、より良い成案を得るという民主主義の本来の姿に立って、政権運営に当たります。
令和7年度予算や税制改正、さらには社会保障や教育など多分野の施策について、多くの御賛同が得られるよう、説明を尽くしてまいります。各党の御主張も十分に拝聴し、議論を重ねます。中長期的な政策の方向性や制度の持続可能性についても、給付や負担の在り方を含め、真摯に議論をいたしてまいります。
国民の皆様、並びに、この場に集う全国民を代表される国会議員の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。