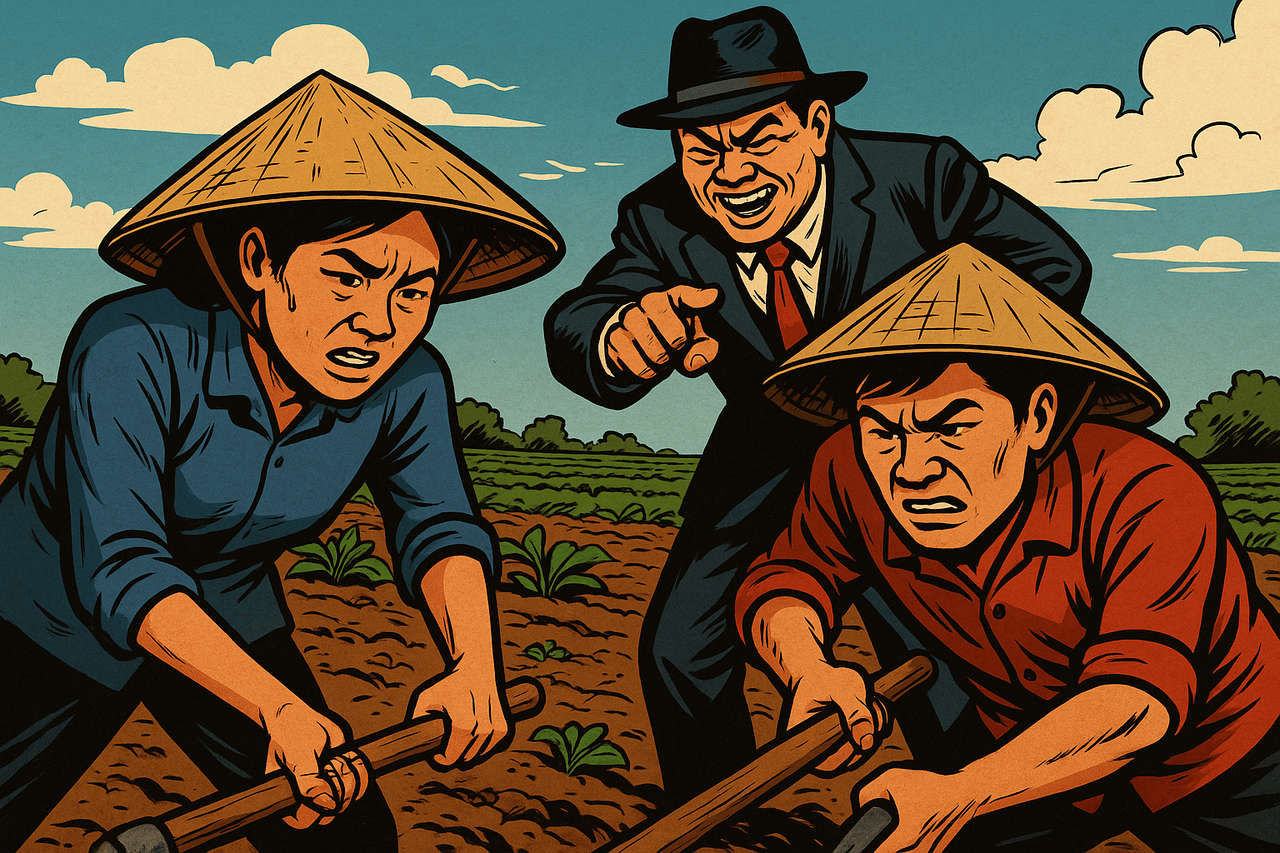中国籍帰化者が過去最多に―韓国・朝鮮を初めて逆転、南アジア勢も急増する日本国籍取得の現実
- 2025/7/19
- 報道・ニュース
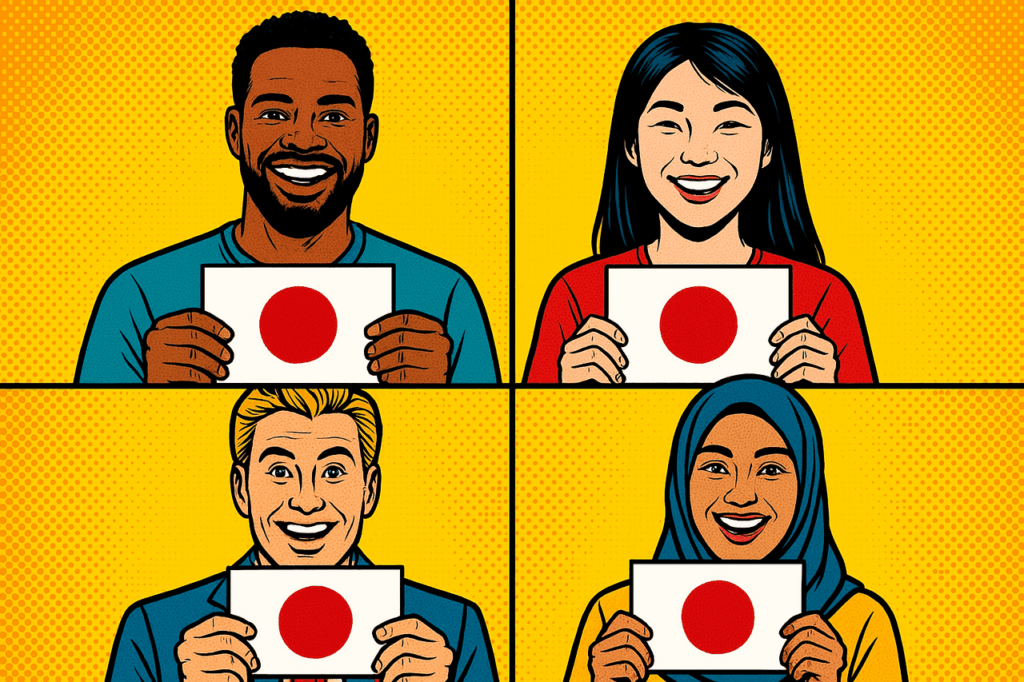
中国籍の帰化者、初めて最多に
南アジア勢の急増も―背景に「日本永住」志向と制度緩和
昨年、日本国籍を取得した中国人が韓国・朝鮮籍を上回り、初めて帰化者数で最多となった。
法務省が発表した令和6年(2024年)の帰化許可統計によれば、日本国籍を新たに取得した外国人のうち、中国籍が3,122人で最も多くなり、長年トップだった韓国・朝鮮籍の2,283人を初めて上回った。帰化制度が整備され始めた昭和48年以来、約50年にわたって続いてきた構図がここで大きく転換したことになる。
帰化許可総数は8800人超、南アジア系も急増
昨年1年間の帰化許可者総数は8,863人。これは近年の平均的な水準(7,000~9,000人)に収まっているが、注目すべきはその国籍構成の変化だ。従来は中韓2カ国が全体の大半を占めていたが、ここ数年でネパールやスリランカ、ミャンマーといった南アジア諸国出身者が急増しており、今年は「その他の国籍」の帰化者が3,458人にまで達している。これは5年前の約1,700人からちょうど倍増している計算だ。
特にネパール人の帰化は急ピッチで進んでおり、令和元年時点ではわずか100人程度だったが、令和6年には600人近くまで跳ね上がった。これには技能実習生や留学生として来日した若年層が、日本社会に長く定着し「永住より帰化のほうが安定的」と判断するケースが増えている背景がある。
韓国・朝鮮籍の帰化者が減少した理由
「特別永住者の帰化が減っていることが一因」
法務省関係者はそう説明する。戦後に在日外国人として特別永住資格を付与されてきた韓国・朝鮮籍の人々が、長年にわたり帰化申請を進めてきたが、世代交代や個人のアイデンティティの問題もあり、近年は申請数そのものが鈍化している。さらに、社会的な風向きの変化や韓国・北朝鮮情勢の影響もあり、「無理に帰化しなくても生活には支障がない」との意識も広がっているとみられる。
中国籍帰化の背景には「現実的な選択」
一方で中国籍の帰化者が急増している背景には、2つの要素がある。まず第一に、在留中国人の母数が大きくなっている点だ。2024年現在、日本に滞在する中長期在留中国人は約84万人で、ベトナム人や韓国人を大きく引き離してトップとなっている。
そして第二に、「日本に残るには永住権よりも帰化の方がメリットが大きい」と考える人が増えている点だ。永住者は在留資格の更新が不要である一方、法的にはあくまで「外国籍」であり、選挙権・被選挙権がないなどの制約がある。その点、日本国籍を取得すれば、社会の一員として全面的に参加できるメリットがある。
「永住ビザより簡単」
このような認識も一部で広がっている。実際には帰化の審査には一定のハードルがあるものの、長期的に日本で働き、家族を持ち、教育を受けた外国人にとっては、「永住より帰化」が現実的な選択肢となってきているのだ。
日本の帰化条件は?
日本の帰化制度には、具体的な審査基準や標準処理期間は公表されていない。法務省も「一律の審査期間は存在しない」としており、不許可となった場合の不服申し立て制度も用意されていない。
ただし、申請に必要な一般的条件として以下の6項目が挙げられている:
- 正当な在留資格で日本に5年以上継続して居住していること
- 18歳以上であること
- 素行が良好であること
- 安定した収入があり、自立した生活ができていること
- 元の国籍を放棄する意思があること(二重国籍は認められない)
- 日本国憲法を尊重する姿勢があること
加えて、日本語での日常会話、読み書き能力も求められる。ただし、明文化された語学試験があるわけではなく、法務局の担当者との面談で判断されることが多い。
審査体制は逼迫気味、半年以上待つケースも
都市部では帰化申請が急増しており、例えば東京都内では初回面談の予約が半年先まで埋まっているという声も出ている。これは明らかに審査体制のキャパシティを超えており、「人手不足による処理遅延」が制度上の課題として浮上している。
帰化を通じて多様化する日本社会
今回のデータが示すのは、日本が「単一民族国家」という建前から、より現実的な「多民族国家」へと歩みを進めつつあるという事実だ。経済界では人手不足への対応策として、外国人材の活用が加速している。帰化による国籍取得は、その先にある「日本社会への定着」を意味する。
今後さらに帰化が進めば、選挙権を持つ新たな有権者層として、政治や社会のあり方にも少なからぬ影響を与えることになるだろう。
- 中国や南アジア出身の新たな「日本人」の社会参加がどう進むか
- 帰化制度の審査体制が、急増にどう対応するのか
- 二重国籍禁止の原則をどう見直すかという政治的議論の行方
「日本は、これからどんな国になっていくのか」
この問いに向き合う時、帰化のデータは単なる統計ではなく、日本の未来の輪郭を浮かび上がらせる鏡といえる。