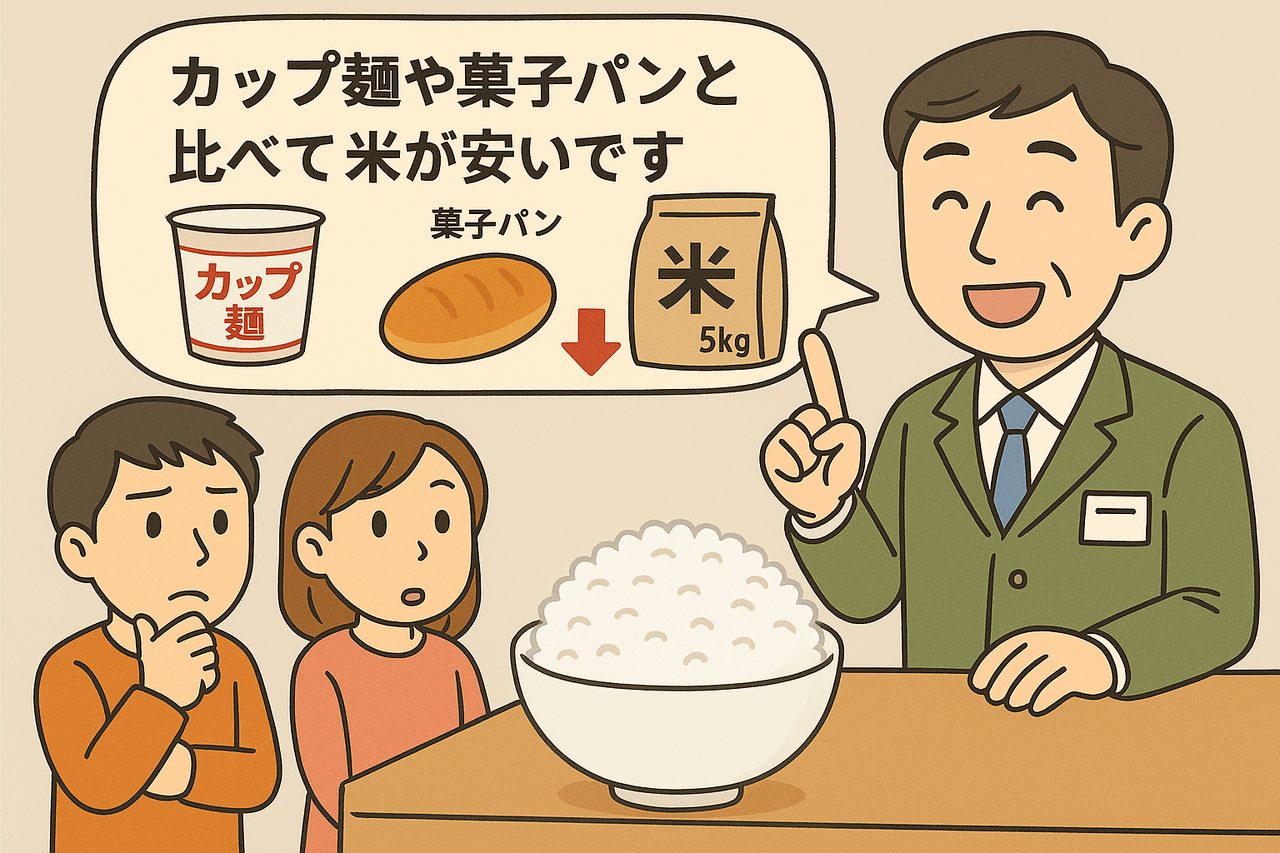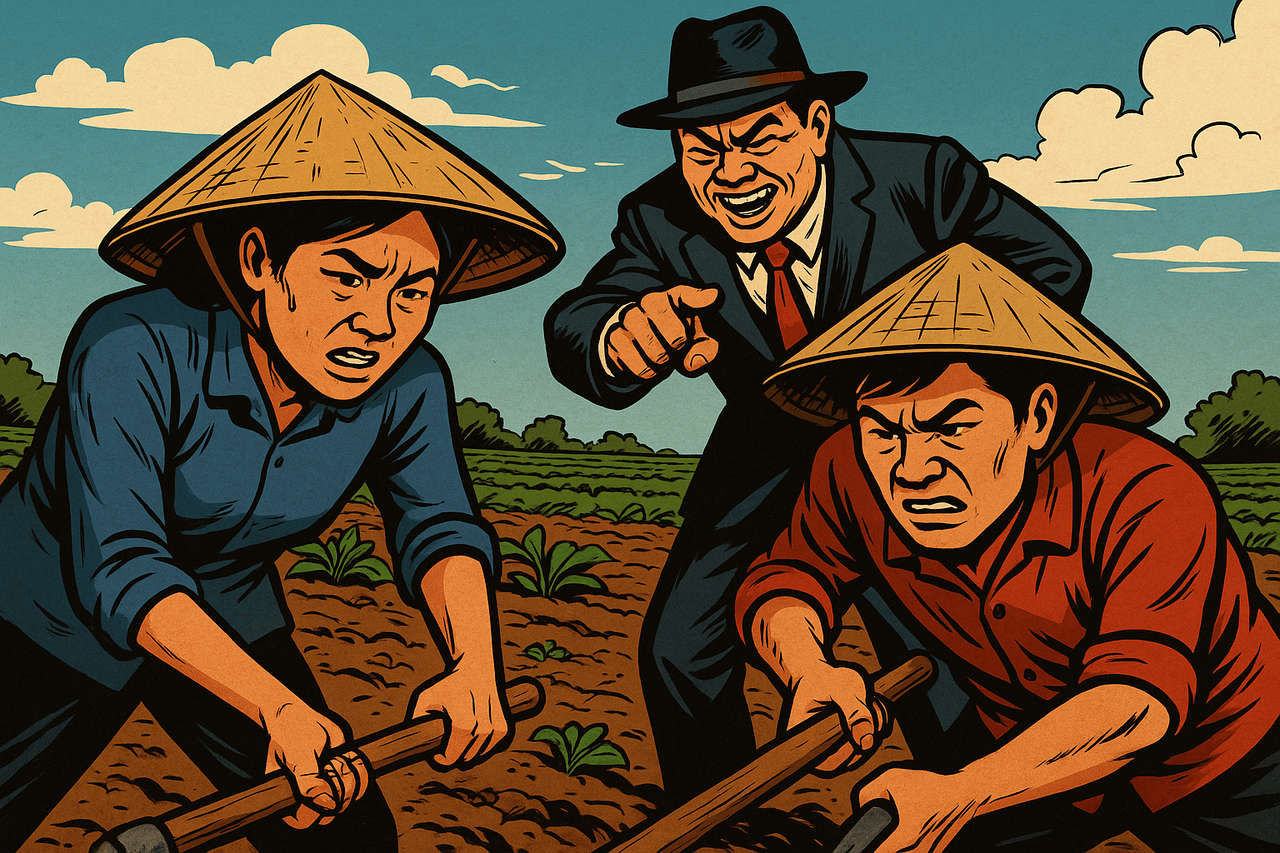日本の観光業とオーバーツーリズム:観光客数の増加とその影響
近年、日本の観光業は急速に成長しており、観光客の数は過去数十年で大きな増加を見せました。
この成長は日本経済にもプラスの影響を与えているような報道をよく見かけます。
しかし、その一方で観光客の過剰集中、いわゆる「オーバーツーリズム(過剰観光)」が問題となっています。
オーバーツーリズムは、観光地やその周辺地域における地元住民の生活に悪影響を及ぼし、渋滞や交通問題、環境への負担などさまざまな問題を引き起こしています。この記事では、観光業の成長、観光客数とGDPの関連性、そしてオーバーツーリズムが引き起こす社会的・経済的な問題について考えてみます。
観光業の成長とGDPへの影響
日本における観光業の成長は、特に2010年代から顕著に見られます。訪日外国人客数は、2010年の約830万人から、2019年には約3180万人にまで増加しました。
観光庁は「観光立国」を掲げ、観光業のさらなる振興を目指してきました。特に、訪日外国人観光客が増加したことにより、地方経済への波及効果も期待されています。
観光業は日本のGDPの一部ではありますが、GDP全体に占める観光業の比率(約2~3%)は相対的に小さいため、観光客数の増減がGDP全体に大きな影響を与えるわけではありません。
そのため、観光客数が増えたとしても、GDP全体に与える影響は限られているのが現状です。
そして、観光業の急成長には一定のリスクも存在します。
観光客の増加が過剰になると、地元住民や観光地への負担が大きくなり、オーバーツーリズムの問題が深刻化します。これは、観光客数が急増することで、観光地の施設やインフラが過剰に利用され、地元住民の日常生活に支障をきたすことを指します。
こちらは、観光客数とGDPの前年度比の変化率を含む表です。
| 年度 | 観光客数(百万) | GDP(兆円) | 観光客数 前年度比(%) | GDP 前年度比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 13.41 | 495.5 | – | – |
| 2015 | 19.74 | 505.5 | 47.20 | 2.02 |
| 2016 | 24.04 | 516.8 | 21.78 | 2.24 |
| 2017 | 28.69 | 530.2 | 19.34 | 2.59 |
| 2018 | 31.19 | 540.6 | 8.71 | 1.96 |
| 2019 | 31.88 | 554.9 | 2.21 | 2.65 |
| 2020 | 4.12 | 532.2 | -87.08 | -4.09 |
| 2021 | 10.97 | 514.9 | 166.26 | -3.25 |
| 2022 | 18.42 | 527.3 | 67.91 | 2.41 |
| 2023 | 27.48 | 535.8 | 49.19 | 1.61 |
コロナ禍において、日本の観光業は大きな打撃を受けました。訪日外国人観光客数は急激に減少し、2020年には前年比で約87%の減少となりました。
しかし、GPDは4%しか減っていません。その翌年は166%増しの観光客になっていますが、GDPは3%減です。
観光業が占めるGDPの割合は約2~3%程度と言われています。観光客数はGDPにはほとんど影響していない事が上の表からわかります。
しかし、その2~3%程度の現在で既に、観光地の住民は不便を強いるのです。
報道では「観光が地元に貢献している」といった内容が流されたりもしますが、全くそういう事はありません。
むしろ、観光客が増えすぎたことによる経済損失の方が大きいと考えます。
地元住民への影響とオーバーツーリズムの問題
オーバーツーリズムが最も顕著に影響を与えるのは、観光地に住む地元住民です。
観光地の一部では、観光客の急増により、地元住民の生活が困難になることがあります。
例えば、住宅地の近くに観光施設が多く建設されると、騒音や人の多さが住民にとっては大きなストレスとなります。
また、観光地の商業施設や飲食店が増えることで、地元の小規模な店が経営難に陥ることもあります。観光業が支える経済が地域の特性を変えてしまうことがあり、観光地の「商業化」や「均質化」が進むことで、地元住民のアイデンティティが損なわれる場合もあります。
特に、都市部では観光客の急増が地元住民に対する迷惑行為を引き起こすこともあります。例えば、観光地では長時間並ぶことが常態化し、地元住民が公共の場を使う際に不便を感じることが増えます。
夜遅くまで観光客の騒音が続いたり、ゴミが散乱したりする問題もあります。また、観光業の需要に応じて住民の住環境が変化することもあります。
観光施設の開発や宿泊施設の増加により、住宅が観光用に転用され、住民の生活環境が脅かされることもあります。
渋滞と交通問題
観光業の拡大に伴い、特に観光シーズンにおける渋滞が問題となっています。
日本の主要観光地では、観光バスや個人の車両による交通量の急増が、交通渋滞を引き起こし、住民や観光客に不便を与えています。
都市部や観光地周辺では、観光バスやタクシー、レンタカーの使用が集中するため、交通渋滞が発生し、移動時間が大幅に増加します。これにより、観光客が訪れる場所が混雑し、快適な観光体験が難しくなることがあります。
特に、観光地での駐車場不足も大きな問題です。
レンタカーを利用する観光客が増加する中で、観光地やその周辺地域で駐車場のスペースが足りなくなり、違法駐車や路上駐車が横行することがあります。
これにより、通行できる道路スペースがさらに狭くなり、渋滞が悪化します。
観光地では、自動車の利用が便利である一方で、過度な車両集中が交通インフラに負担をかけ、渋滞や駐車場不足といった問題を引き起こします。
レンタカー問題と持続可能な観光
レンタカーの利用が増加すると、観光地やその周辺のインフラへの負担がさらに大きくなります。
特に小さな町や観光地では、レンタカーの利用が地域の交通機関に対する影響を与えます。
多くの観光客がレンタカーを利用することで、公共交通機関の利用者が減少し、地域の公共交通の維持が難しくなることもあります。
また、レンタカーを使用する観光客が地元の交通ルールを守らない場合や、迷惑な行動を取ることが問題となります。観光地における道路事情に対する理解が不足している場合、レンタカーによる混乱が生じ、地元住民にとっては大きなストレスとなります。
持続可能な観光を実現するためには、観光業の管理方法を改善し、観光地のインフラを適切に整備する必要があります。
観光客数を適切に管理し、観光地での過剰な混雑を防ぐためには、観光客の分散化や、代替的な観光地の開発、公共交通の充実などが求められます。さらに、レンタカー利用者に対しても、環境に配慮した移動手段の提案や、地域ごとの交通ルールの遵守を促す取り組みが重要です。
観光客を誘致することには一時的な経済的利益があるものの、地元にとっての利益は限定的であり、むしろデメリットが大きい場合が多いです。
観光業で得られる収益は主に観光施設や外部業者に集中し、地元住民や中小企業への波及効果は少ないことが多いです。
観光地が過密化すると、住民の生活環境が悪化し、騒音やゴミの問題が発生します。さらに、観光施設の増加により住宅価格が上昇し、地元住民の生活コストが増加することもあります。
これらを考慮すると、観光業がもたらす経済的利益は小さく、その負担(経済損失)の方が大きいと言えます。