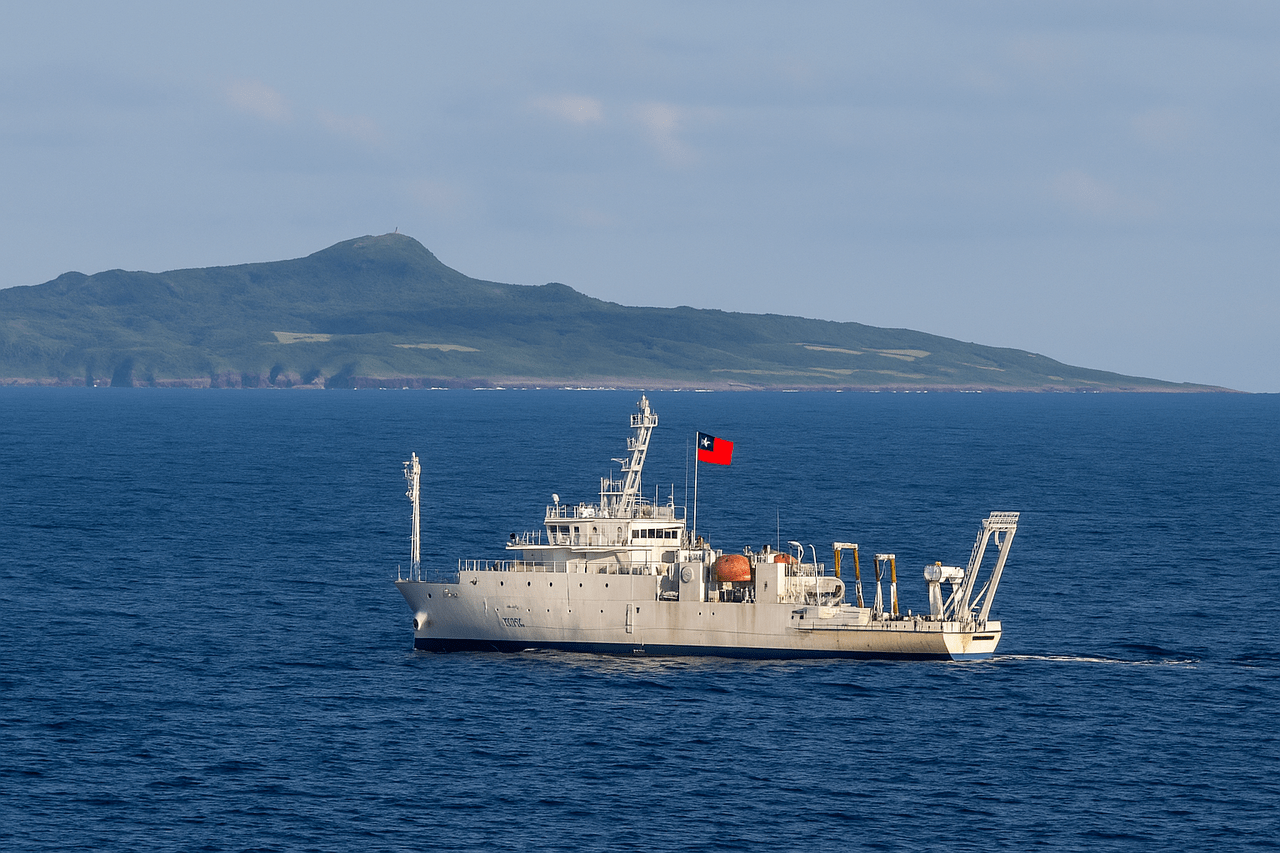【移民頼みの少子化対策に潜む落とし穴】──“出生数が伸びた国”でも自国民の赤ちゃんは減っている
- 2025/7/14
- 記事

「北欧並みの手厚い福祉を導入すれば、日本の出生率もV字回復できるはずだ」。そんな声が最近、政界やメディアでしばしば聞こえてくる。だが統計を細かくのぞき込むと、ひと筋縄では語れない現実が浮かび上がる。北欧でいま起きているのは、“総出生数の見かけ”と“内訳”のギャップ──増えているのはもっぱら移民家庭の赤ちゃんであり、現地で生まれ育った自国民の赤ちゃんはむしろ加速度的に減っているという事実だ。
数字の帳尻合わせが生む“増えたように見える”現象
まず、最新の出生数を俯瞰しよう。
- ノルウェー
- 2023年の総出生数は 51,980人。
- うち約11,900人が移民家庭の赤ちゃんで、全体の22.9%に達する。
- フィンランド
- 2023年の総出生数は 43,320人。
- うち5,000〜7,000人前後(統計の切り口により変動)が移民系で、割合は15〜17%と推計される。
表面上は「出生数が持ち直した」と言われるが、それは “移民出生の上積みで帳尻を合わせている” にすぎない。自国民だけを切り出すと、ノルウェーでは2022→23年に約2,000人も減り、フィンランドも同様に下げ止まらない。
なぜ移民家庭の出生率は高いのか
- 年齢構成
多くの移民女性は20代前半で第一子を産む。晩婚化・非婚化が進む自国民より“出産適齢期”人口が厚い。 - 価値観と宗教背景
イスラム圏やアフリカ出身の家庭では「3人・4人は当たり前」という文化規範が根強い。 - 経済インセンティブ
北欧の手厚い児童手当や家賃補助は、所得水準の低い移民世帯ほど相対的メリットが大きい。 - ネットワーク効果
移民コミュニティでは大家族モデルが“ロールモデル”として可視化されやすく、出生意欲が維持されやすい。
もちろん好ましい面もある。移民は労働人口を下支えし、多文化的な刺激を社会にもたらす。しかし「出生数を底上げ=少子化対策成功」という単純図式は成り立たない。
移民頼みの危うさ──“第二世代”の壁
経験豊富な人口学者ほど口をそろえるのが 「第二世代で出生率は現地化する」 という鉄則だ。事実、スウェーデンやデンマークでは、移民一世が3人以上産んでも、その子ども世代になると出生率は1.6前後に急低下するという研究が相次ぐ。
数字で先延ばししているだけ
福祉コストは雪だるま式に膨らみ、多言語教育や住宅インフラの追加投資も不可避。10~20年後に再び出生率が沈めば、追加コストだけが残る。
北欧でも鳴り響く“警報”
ノルウェーの合計特殊出生率(TFR)は 1.40 に下落し、過去最低を更新。各紙は「9カ月の有給育休も住宅手当も効かない」と悲鳴を上げる。
フィンランドは記録的低水準の 1.26。国立統計局は「1776年以来最少」と指摘する。
欧州全域を見回しても平均TFRは 1.38 と、人口維持ラインの2.1から遠く離れたままだ。
日本への示唆:本当に必要なのは“暮らしの安心”
日本でも「労働力不足の解消」として移民受け入れ拡大が議論される。しかし北欧の事例は、移民流入=少子化対策の万能薬ではないことを雄弁に物語る。
- 賃金と雇用の安定
若い世代が“将来設計”に踏み切れる水準へ底上げ。 - 住宅コストの抑制
家賃補助だけでなく、都市計画で“子育て家族向け”の適正家賃ゾーンを確保。 - 長時間労働是正と柔軟な働き方
育休・時短制度だけでなく、男女ともに“キャリアの致命傷にならない”企業文化へ。 - 教育費の負担軽減
高等教育無償化や給付型奨学金の拡充で、「子ども1人あたりコスト」の心理的ハードルを下げる。
これらの“土台工事”に本腰を入れない限り、数字は一時的に改善しても、やがて元の木阿弥になるだろう。
数字の裏にある「誰が産んだか」を見よ
出生数の棒グラフが少し右肩上がりになった――それだけで大臣が胸を張る光景は簡単に想像できる。だが、その増分が 「移民家庭の赤ちゃんか、それとも自国民の赤ちゃんか」 を見極めなければ、本質を見誤る。
北欧モデルは参考になる部分が多い。それでも “数字のトリック” まで輸入してはならない。
「出生数が増えた」と喜ぶ前に、その数字の意味を問い直す――。
日本が本当に学ぶべきは、 「なぜ自国民が産まなくなったのか」 という核心に、正面から向き合う勇気だ。人口減少という長い坂道を上り返すには、移民の力と同時に、自国民が「産みたい」と自然に思える社会基盤を築く以外に近道はない。