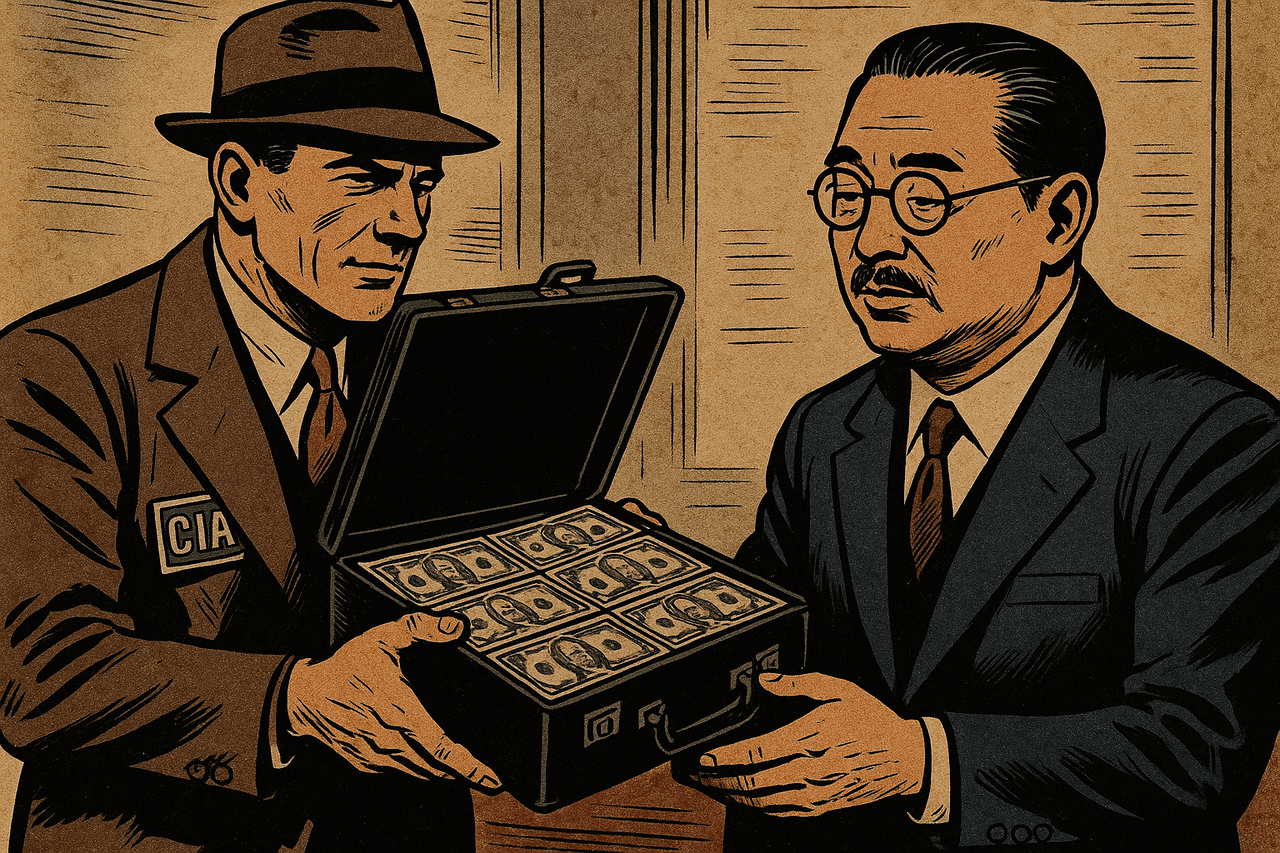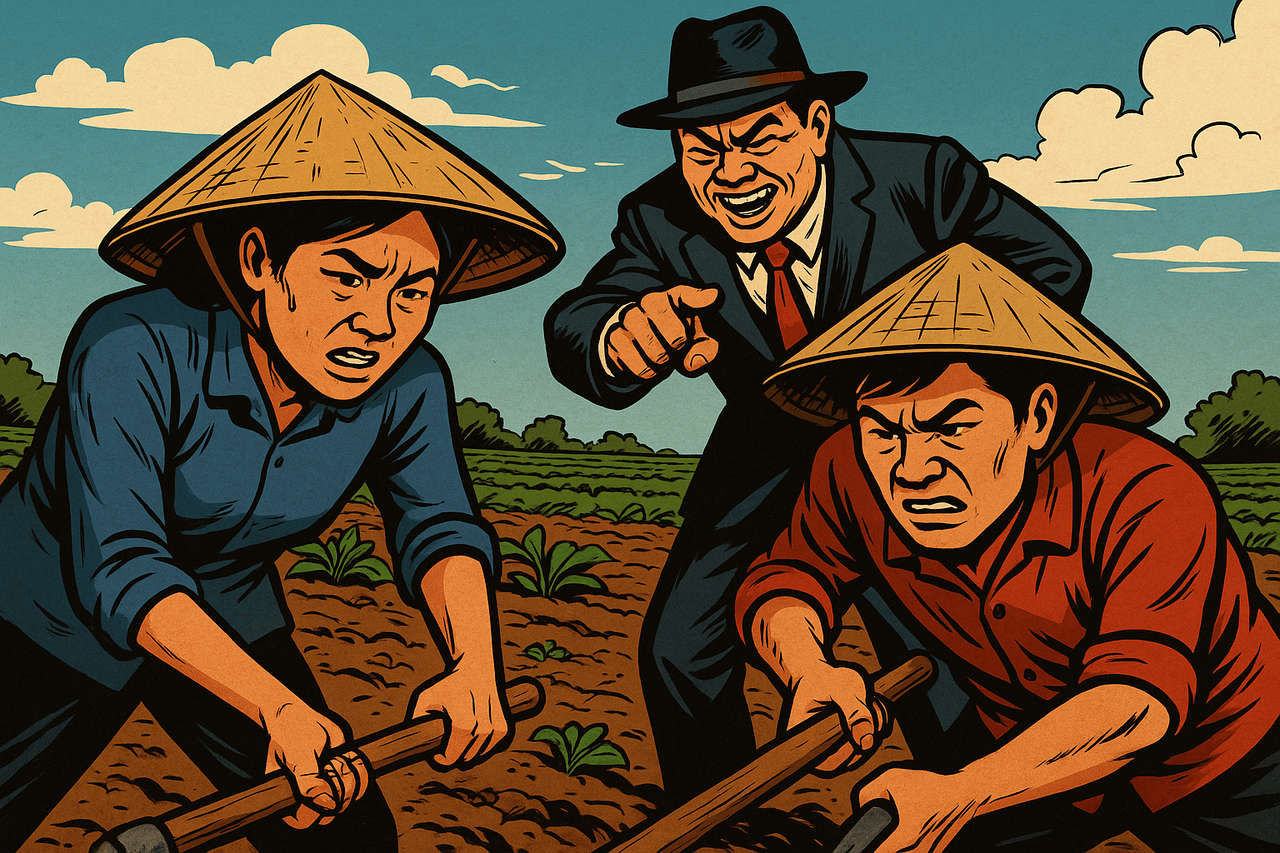洋上風力に立ちはだかる現実 三菱商事の巨額損失が突きつけた問い
真っ青な海と空、そして白く輝く巨大風車――。そんな清々しいビジュアルが印象的な風力発電の広告を、最近よく目にするようになった。環境に優しく、未来志向。そんなイメージで語られる「洋上風力発電」が、今、日本でも本格導入に向けて動き出している。だが、その舞台裏では、想像以上に厳しい現実が立ちはだかっている。
三菱商事、まさかの522億円減損
今年2月、三菱商事が突如発表したのは、国内3海域で進めていた洋上風力発電プロジェクトに絡む522億円の減損処理。これは2024年度の4~12月期連結決算に大きく響き、同社の風力事業が大きな壁に直面していることを裏付けた。
同社が手掛けていたのは、秋田県と千葉県沖での洋上風力。2021年の公募で落札した際は、あまりに低い価格提示が話題となり、「総取り」とも言われたが、その後の世界的な資材価格高騰や円安、建設コストの急上昇が重なり、採算は崩壊。事業は暗礁に乗り上げた。
会見で中西勝也社長は「インフレなど想定以上の外的要因が押し寄せた」と説明しつつ、「再エネへの挑戦にブレーキをかけるものではない」と強調した。
「再エネ万歳」で済まされない現実
だが問題は、このニュースがメディアで大きく取り上げられていないことだ。日本経済新聞は「洋上風力、日本も試練」(2月7日)と報じたが、三菱商事の説明をそのまま伝えるにとどまり、現場取材や独自の分析には乏しい。
環境にやさしい、クリーンで持続可能――そうした再生可能エネルギーへのポジティブな印象が先行しがちだが、裏側には地に足のついた実態と向き合う必要がある。
朝日新聞の報道データベースで調べると、2024年度の記事件数で「風力発電」が196件だったのに対し、「原発」は2576件。数字がすべてではないが、再エネの現場を丹念に追いかける意志がどこまであるのか、正直疑問は残る。
日本の洋上風力に立ちはだかる構造的課題
そもそも、洋上風力発電には構造的な難しさがある。欧州とは異なり、日本近海は急深の海が多く、設置に向かない地形が多い。加えて台風や地震といった自然災害も多く、設備の耐久性や保守点検の手間もかかる。
さらには、日本国内には大型風車の製造拠点が乏しく、タービンや部品の多くは中国や欧州からの輸入に頼っている。結果として、為替や国際物流の影響をもろに受ける構造になっている。
そこにきて、欧米と中国との経済的分断が進む中、今後の調達にもリスクが生じる可能性がある。制度面でも、建設許可や漁業者との調整など、乗り越えるべきハードルは少なくない。
海外でも逆風、オーステッドも巨額損失
実はこの問題、日本に限った話ではない。洋上風力で世界トップを走るデンマークのオーステッドも、昨年末に日本円換算で約2600億円の減損を発表している。理由は三菱商事と同じく、資材や建設コストの高騰だ。
米国や英国でも、風力発電事業の見直しや中断が相次いでおり、欧州主導で進んできた「再エネドリーム」に冷や水が浴びせられているのが実情だ。
知りたいのは「実態」だ
もちろん、再生可能エネルギーの推進が時代の要請であることは間違いない。エネルギー安全保障や脱炭素という大きな課題に向けて、風力発電は重要な選択肢の一つだ。
しかし、その正当性を支えるのは、イメージや理想論ではなく、実態と現実に根ざした議論だ。特に日本のような地形・経済構造では、欧州のモデルをそのまま持ち込むことはできない。
健全な再エネ政策を支えるためにも、報道はもっと深く現場に入って、数字の裏にある人の声や現実を伝えていく必要がある。賛美や批判を越えた“成熟したエネルギー議論”こそ、今の日本社会に必要とされている。