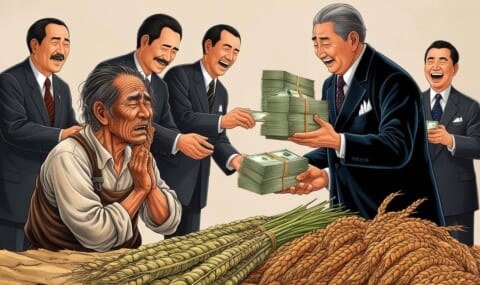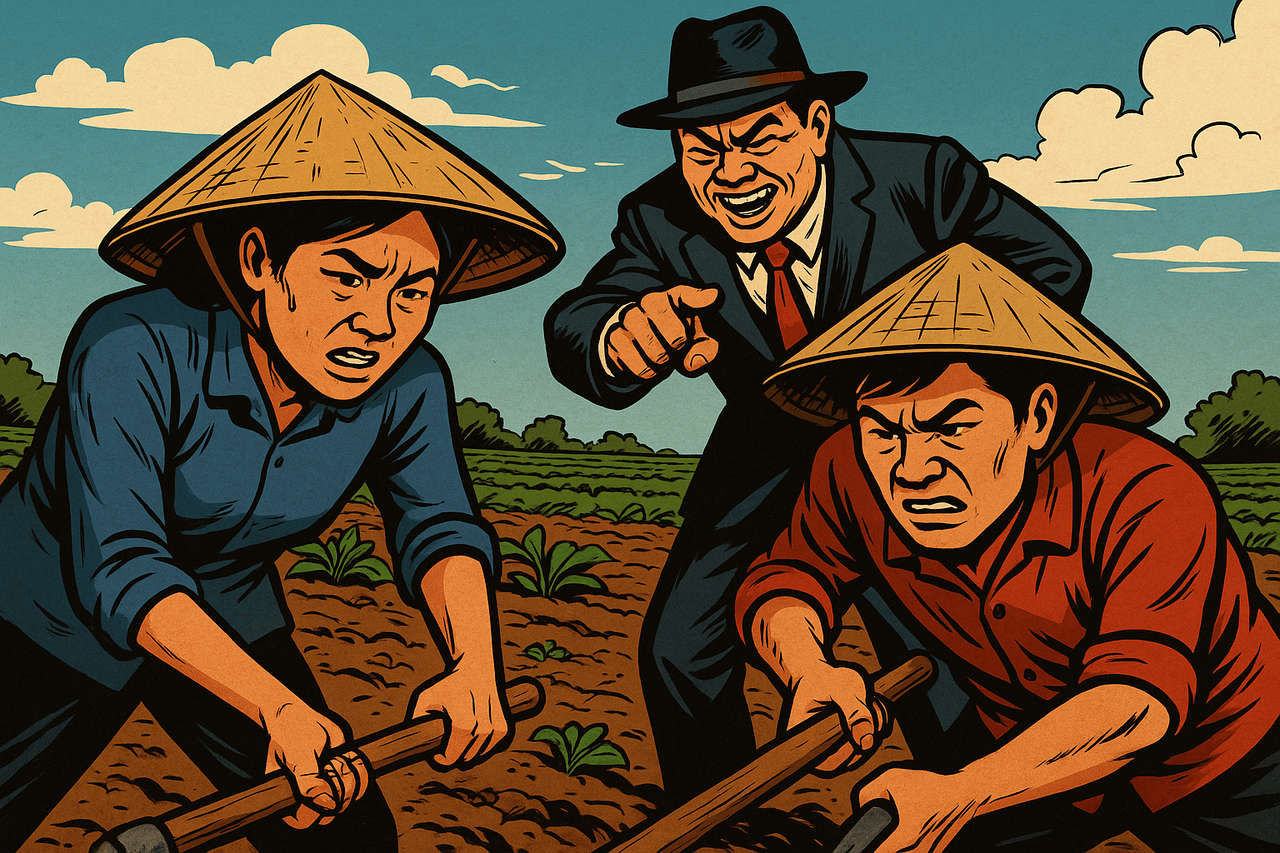減税は全く進まないのに増税はスムーズにいつの間にか決まっているように感じます。
最近は、106万円の壁や103万円の壁などなど色々な情報が報道されています。
“106万円の壁”撤廃に 厚生年金新たに200万人加入対象見込み
上記のような「厚生年金 賃金要件撤廃」が決まるまでの流れを説明します。
厚生年金の賃金要件撤廃に関する流れは、以下のように進むのが一般的です。厚生労働省が政策を提案してから最終的に決定するまで、いくつかの段階があります。
1.案の提示
厚生労働省は社会保障審議会(通常、年金部会)に対し、現行の賃金要件を撤廃する案を提示します。
- 例えば、厚生年金の加入要件に関する見直しが目的。
- 賃金要件(一般的には月収88,000円以上など)を撤廃することで、パートやアルバイトなどの短時間労働者も厚生年金に加入できるようにする狙いがあります。
2.部会での議論
社会保障審議会の年金部会で、提案内容について詳細に議論されます。
- 関係者(企業、労働組合、学者、地方自治体など)の意見を収集。
- 賃金要件撤廃が労働市場や企業の負担に与える影響などが検討されます。
3. 意見公募(パブリックコメント)
社会保障審議会の年金部会での議論後、案の内容を広く国民に公表し、意見募集(パブリックコメント)を実施することが一般的です。
国民や専門家から幅広い意見を収集し、政策の妥当性や懸念点を確認します。
4. 再検討・修正
集まった意見をもとに、必要であれば案を修正します。
撤廃範囲や時期の変更、企業負担軽減策の追加などが考えられます。
5. 閣議決定または法案提出
修正版が完成した後、必要に応じて法案化されます。
- 法改正が必要な場合は国会での審議を経て決定。
- 関連法案が成立した場合は、実施時期や詳細が正式に決定されます。
ここで決定ですので、閣議決定の場合は閣僚、法案提出の場合は賛成・反対したそれぞれの議員名が有権者に伝わるべきです。
議会の採決は賛成・反対の議員名が分かるようにするべき
6. 実施準備と周知活動
制度改正が決まった後、厚生労働省や年金事務所を通じて周知活動を行います。
企業や国民への説明会、パンフレット作成、問い合わせ対応の強化など。
7. 施行
実施時期が到来すると新しい制度がスタートします。
賃金要件撤廃による影響を適切にフォローするため、実施後も調査や追加措置が行われることがあります。
参考データ
社会保障審議会・年金部会のメンバー
| 氏名 | 所属・役職 |
| 出口 博基 | 日本経済団体連合会社会保障委員会年金改革部会長 |
| 小野 正昭 | 年金数理人 |
| 菊池 馨実 | 早稲田大学理事・法学学術院教授 |
| 権丈 善一 | 慶應義塾大学商学部教授 |
| 小林 洋一 | 日本商工会議所社会保障専門委員会委員 |
| 駒村 康平 | 慶應義塾大学経済学部教授 |
| 是枝 俊悟 | 株式会社大和総研金融調査部主任研究員 |
| 佐保 昌一 | 日本労働組合総連合会総合政策推進局長 |
| 島村 暁代 | 立教大学法学部教授 |
| たかまつ なな | 株式会社 笑下村塾代表取締役社長 |
| 武田 洋子 | 株式会社三菱総合研究所執行役員(兼)研究理事 シンクタン |
| 嵩 さやか | 東北大学大学院法学研究科教授 |
| 玉木 伸介 | 大妻女子大学短期大学部教授 |
| 永井 幸子 | UAゼンセン副書記長 |
| 原 佳奈子 | 株式会社TIMコンサルティング取締役社会保険労務士 |
| 平田 未緒 | 株式会社働きかた研究所代表取締役 |
| 深尾 京司 | 独立行政法人経済産業研究所理事長一橋大学特命教授 |
| 堀 有喜衣 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構副統括研究員 |
| 百瀬 優 | 流通経済大学経済学部教授 |
106万円の壁 厚生年金 賃金要件撤廃とは
106万円の壁とは
- パートやアルバイトの短時間労働者が厚生年金に加入する際の基準の一つ。
- 現行の基準では、以下の条件を満たす場合に厚生年金加入が必要。
- 月収が88,000円以上(年収換算で約106万円以上)。
- 労働時間が週20時間以上。
- 勤務先が従業員101人以上(2024年10月以降は51人以上に拡大)。
現行制度の問題点
- 働き方の制限
年収106万円を超えると社会保険料の負担が増え、手取りが減るため、労働時間を調整する人が多い。 - 不公平感
小規模事業所(従業員50人以下)では同じ条件で働いても厚生年金に加入しない場合があり、保険の適用範囲に不公平感がある。 - 老後の年金格差
短時間労働者が厚生年金に加入できないことで、老後の年金受給額に差が生じる。
賃金要件撤廃の動き
- 厚生労働省の案
賃金要件(月収88,000円以上)を撤廃し、短時間労働者の厚生年金加入を拡大する案が示されている。 - 目的
・「働き方改革」の一環として、柔軟な働き方を促進。
・老後の年金格差を是正。
・少子高齢化に伴う年金財源の安定化。
想定される影響
- 短時間労働者の負担増
賃金要件撤廃により、社会保険料負担が増える可能性がある。 - 企業側の負担増
企業も従業員分の社会保険料を負担する必要があり、中小企業を中心にコスト増加の懸念がある。老後の年金増加
厚生年金に加入する労働者が増えることで、将来的には受給額が増えると期待される。