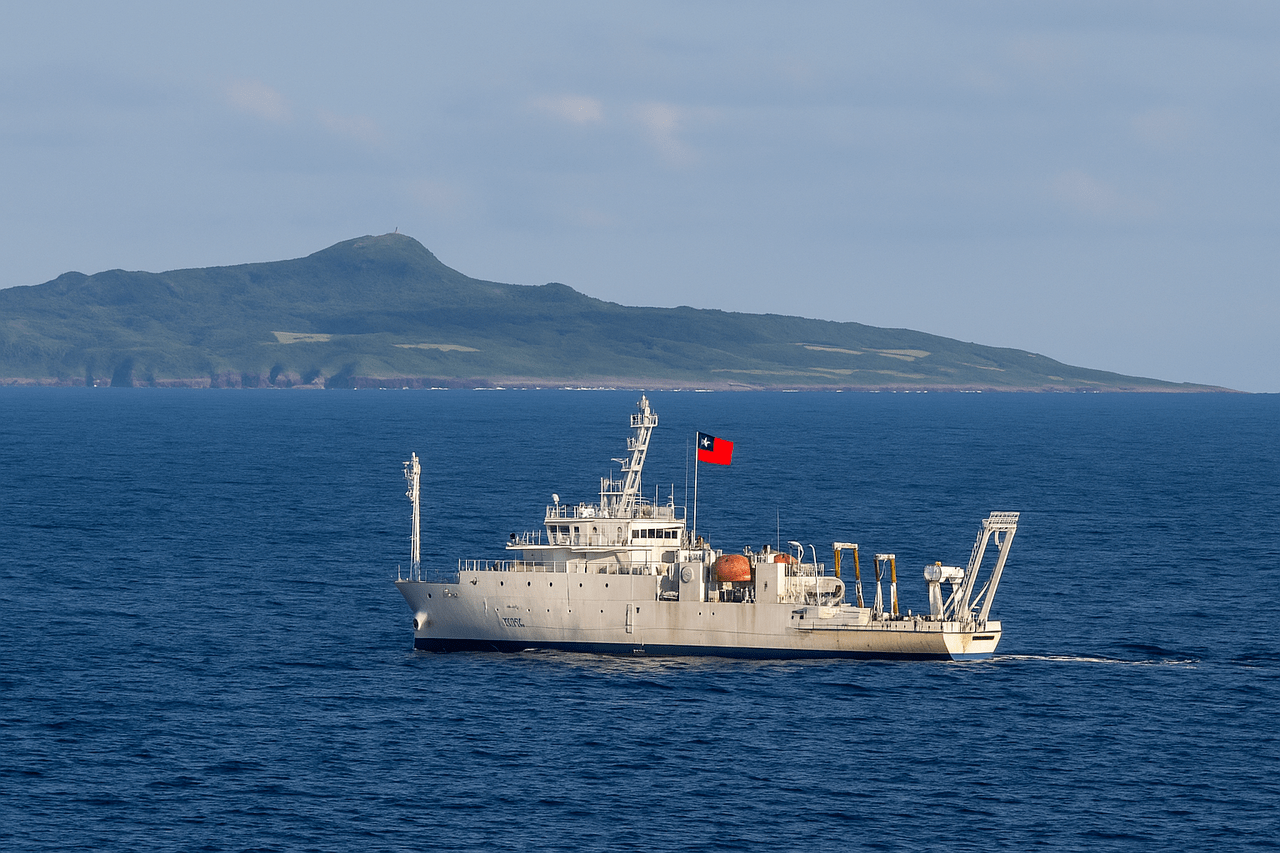無償化では少子化は止まらない:出生率改善の裏にある“移民依存”という現実
- 2025/6/26
- 記事

無償化では少子化は止まらない 出生率上昇の“改善報道”の裏にある移民依存の実態
「保育無償化で子育てしやすい社会へ」「教育費の負担軽減がカギ」──こうした政策スローガンが、少子化対策として繰り返されてきた。しかし、現実はどうか。日本だけでなく、スウェーデンやフランスといった“成功例”とされる国々でも、出生率の改善は一見して起きているようで、実態は大きく異なる。
結論から言えば、保育や教育の無償化といった金銭的支援だけでは、出生率の回復にはつながらない。そして今、多くの先進国で「出生数が増えた」と報じられる背景には、自国民ではなく移民の子どもが増えているという現実がある。
「出生率改善」は本当に政策の成果なのか
近年、スウェーデンやドイツでは出生率が1.7前後まで回復し、「家族政策の成功例」として紹介されることがある。だが、統計の中身を見てみると、その数字の相当部分を移民出身の母親が支えていることがわかる。
ドイツでは、出生数全体の約3割が外国出身の女性によるもので、特にトルコ、シリア、アフガニスタンなどの多産傾向のある文化圏からの移民家庭が多い。スウェーデンも同様で、移民の割合は人口全体の2割を超え、出生率の高い家庭の多くがソマリアやシリアなどから来た人々だ。
またフランスでも、旧植民地からの移民を含むアフリカ・アラブ系住民が出生率を押し上げている。つまり、社会保障制度が整っている国で出生率が比較的高いのは、制度そのものの成果というよりも、移民による人口増が数字を底上げしているという構造的な事実がある。
自国民の出生率は依然として低迷
注目すべきは、こうした“改善”が自国民だけに限定すれば成立しないという点だ。ドイツでもスウェーデンでも、移民でない女性の出生率は日本とほぼ同等、あるいはそれ以下である。つまり、無償化や手厚い制度があっても、それだけで「生む」という選択には至っていないということだ。
日本でも同様の傾向が見られる。2019年に幼児教育・保育の無償化が導入されたが、その後も出生率は1.3から1.2へと下降。経済的支援だけでは出産・育児への心理的ハードルは下がらないという事実を突きつけている。
金銭支援では埋まらない「構造の壁」
そもそも現代の資本主義社会では、出産や子育てに対する価値観そのものが変わっている。「合理性」や「個人の選択」が尊重される社会では、キャリアや自己実現を優先する人が増え、子どもを持つことが“非効率”とみなされがちだ。
特に女性の高学歴化や都市部での生活コスト、非正規雇用の広がりなどが、「産む・育てる」という選択を遠ざけている。保育園が無料になっても、仕事と育児の両立が現実的でなければ意味がない。周囲のサポートが乏しく、孤独な子育てに耐える覚悟が求められる社会では、いくら現金を渡しても状況は変わらない。
「1,000万円給付」でさえ届かない現実
一部では「子ども1人につき1,000万円を支給すれば少子化が止まるのでは」という提案もある。しかし、海外の研究や過去の実例から見ても、金銭インセンティブは出生の「タイミング」を動かす効果はあっても、出産そのものを大幅に増やす力は持たない。
実際、フランスでは子ども1人あたり500万円相当の支援があるが、それでも出生率は2.1に届かない。日本でも、1,000万円を給付した場合のシミュレーションでは、出生率は1.2から最大でも1.6前後までしか上昇しないとされる。
「移民を受け入れずに少子化を改善した先進国は存在しない」
そして最も重要な点は、移民を受け入れずに、自国民のみで出生率を回復させた資本主義国家は、現在まで存在しないという事実だ。スウェーデン、ドイツ、フランス、カナダ、イギリス……いずれの国も出生率の維持には移民の存在が不可欠になっている。
例外的に高い出生率を維持しているイスラエルは、宗教的・民族的な要因が強く、資本主義先進国の中では特殊な位置づけにある。また、イスラエルもまた、世界中のユダヤ人を対象とした“帰還移民”を国家政策として取り入れており、純粋な自国民だけで人口維持しているわけではない。
少子化対策に必要なのは「構造改革」と「価値観の転換」
保育の無償化や現金給付は、政策としては重要な基盤だ。しかし、それだけで社会の出産行動が大きく変わることはない。今求められているのは、制度に加えて、
- 子育てしながら働き続けられる雇用制度の再設計
- 出産・育児が個人に偏らない社会的分担
- キャリアを犠牲にしないライフデザイン
- 「子を持つ生き方」を合理的な選択肢に戻す文化の再構築
といった、より深い構造と価値観へのアプローチだ。
「数字」に惑わされず、“中身”を見るべきとき
出生数や出生率が一見上がっている国があるからといって、それが「成功例」とは限らない。移民による人口増を、自国民の少子化対策と混同すべきではない。
今後の政策議論では、単なる「無償化」や「給付額」ではなく、それが「誰のための制度か」「どの層に実効性があるのか」という視点こそが重要になる。少子化の本質的な克服には、制度の設計を見直すだけでなく、社会そのものの“空気”を変える必要があるのではないだろうか。