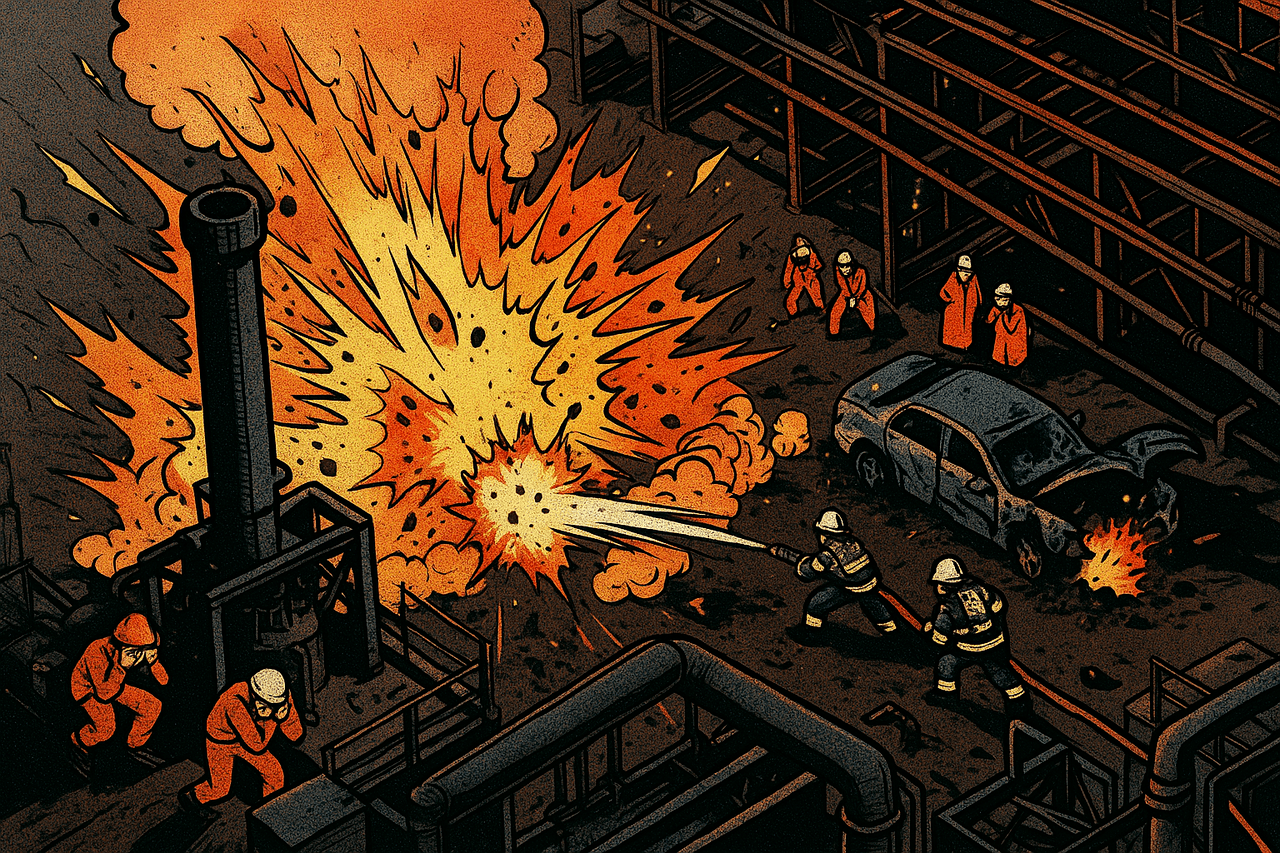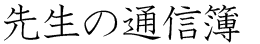2024年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、2026年4月から新たな「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。
この制度は、少子化対策の財源を確保するため、医療保険の保険料に上乗せして徴収されるもので、年収400万円の会社員で月額650円、年収600万円で月額1000円など、負担額の目安が示されています。
しかし、この制度に対しては、独身者や子どもを持たない夫婦から「なぜ自分たちも負担しなければならないのか」という声が上がり、ネット上では「独身税」ではないかとの批判が広がっています。評論家の真鍋厚氏は、このような少子化対策に対するネガティブな反応は珍しくないものの、子ども・子育て支援金制度には、独身者や子どもがいない夫婦に対する無自覚な差別を助長する側面があると指摘しています。
独身者が負担を強いられる制度
子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源確保を目的として、医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。負担額の目安は、年収400万円の会社員で月額650円、年収600万円の会社員で月額1000円などとされています。しかし、子育てを終えた人や子どもを持つ予定のない人にとっては、この負担は納得しがたいものがあります。このような仕組みから、「子育て支援税」という名称が適切ではないかとの意見も出ています。
税制における独身者の不利な立場
税制において、独身者と既婚者では適用される所得控除が異なり、既婚者の方が多くの控除を受けられるため、実質的に独身者が不利な立場に置かれていることが指摘されています。この背景には、「所帯を持つのが当たり前」という価値観が根強く残っていることが挙げられます。戦後の日本社会では、「国民皆婚」による家族形成が標準とされ、諸制度もそれを支える形で整備されてきました。
社会的な偏見と差別意識
未婚者や子なし夫婦に対する偏見や差別意識は、日本社会に深く根付いています。例えば、大阪の企業が「独身の人は信用しない」と公言し、非難を浴びたケースがありますが、これは氷山の一角に過ぎません。多くの場面で、結婚や子育てをしていない人々に対する偏見が存在します。このような差別意識は、「子どもを持つことが社会的責任である」という考え方から来ているとされています。
社会の分断と今後の課題
今回の子ども・子育て支援金制度に対する批判は、未婚者や子なし夫婦がこれまで経験してきた不当な扱いに対する反発とも受け取れます。さらに、1990年代から続く経済停滞により、家族形成が困難になり、「所帯を持つこと」が一部の特権となっている現状も影響しています。ライフスタイルの多様化が進む中で、結婚や子育てが「趣味」のように扱われる傾向もあり、新たな税負担に対する理解は得られにくい状況です。
子ども・子育て支援金制度は、少子化対策として重要な役割を果たす一方で、独身者や子なし夫婦への負担増加や差別意識の助長といった課題も浮き彫りにしています。これらの問題を解決するためには、税制や社会制度の見直し、そして何よりも社会全体の価値観の変革が求められます。多様なライフスタイルが尊重される社会を目指し、今後の政策や社会的取り組みが注目されます。