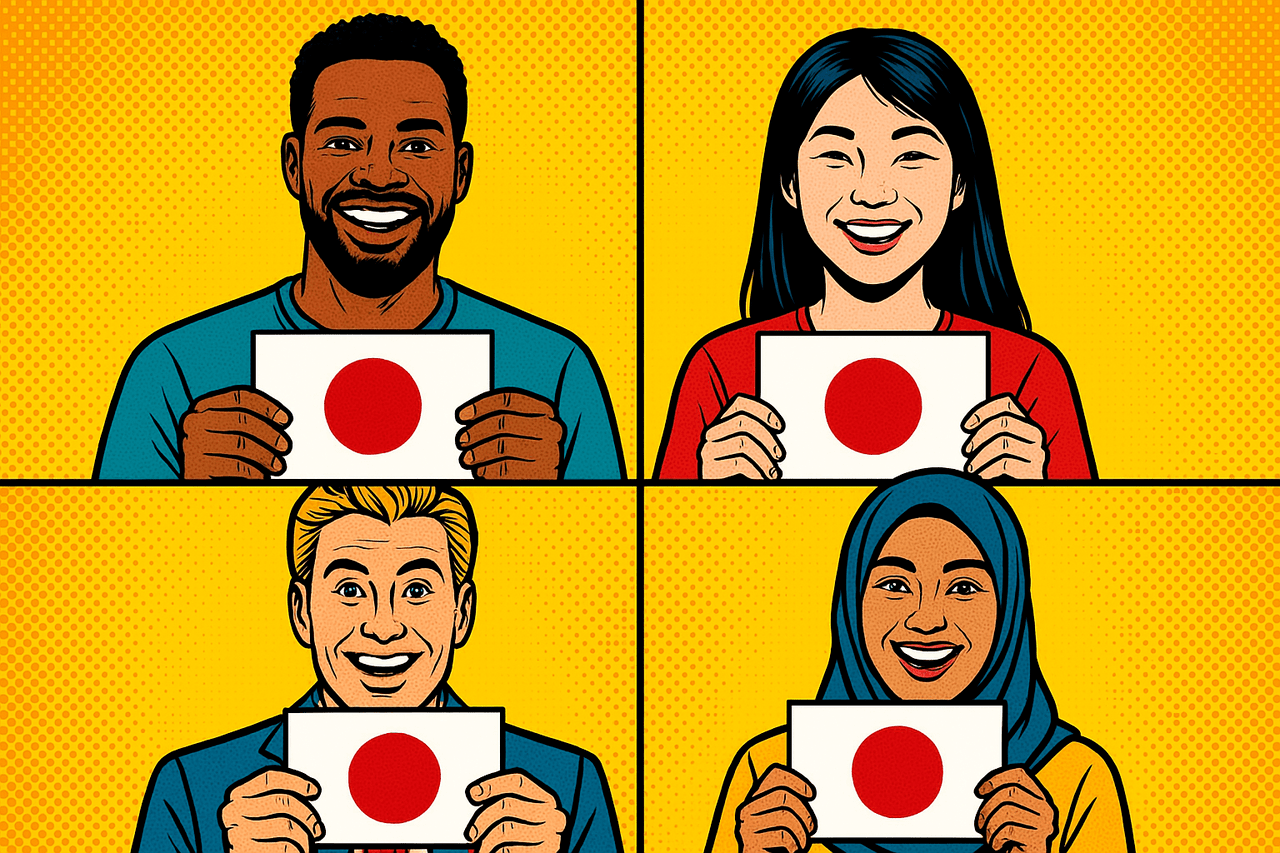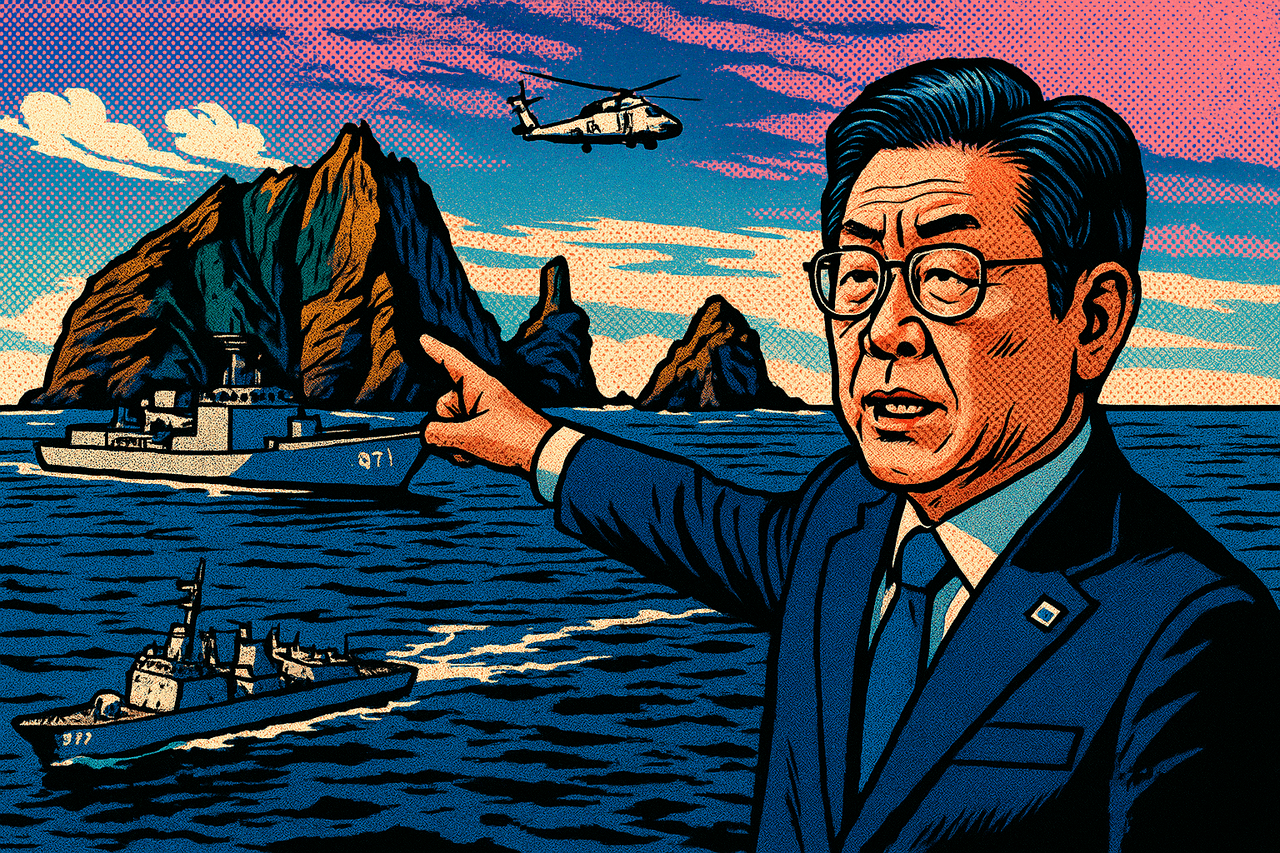石破茂首相が表明した対米1兆ドル(約150兆円)の投資計画について、一部では日本の税金を用いるのではないかとの懸念が見られます。しかし、首相の発言は政府資金ではなく、民間企業による投資を指しています。実際、石破首相は「アメリカにとって日本が過去5年連続で最大の投資国だ」と述べ、日本企業の対米投資意欲が高まっていると指摘しています。
日本企業の対米投資は近年、着実に増加しています。米国商務省のデータによれば、2023年末時点での米国の対内直接投資残高は前年比4.4%増の5兆3,941億ドルとなり、その中で日本は5年連続で最大の投資元となっています。具体的には、日本からの投資残高は前年比2.9%増の7,833億ドルで、全体の約14.5%を占めています。
| 年度 | 投資残高(億ドル) | 前年比増加率(%) |
|---|---|---|
| 2019年 | 6,500 | 5.0 |
| 2020年 | 6,700 | 3.1 |
| 2021年 | 7,000 | 4.5 |
| 2022年 | 7,300 | 4.3 |
| 2023年 | 7,833 | 7.3 |
(注:2023年のデータは米国商務省の発表に基づく)
業種別に見ると、製造業が全体の41.2%を占め、特に化学、輸送機械、コンピュータ・電子製品、卸売業などで投資が増加しています。例えば、化学分野では、武田薬品工業が米バイオ医薬品企業ニンバス・ラクシュミを60億ドルで買収するなど、大型の投資案件が見られます。また、自動車関連では、トヨタ紡織がケンタッキー州に新工場を建設する計画(2億2,500万ドル)や、日立アステモが同州の生産拠点を電動化に向けて拡張する投資(1億5,300万ドル)などが進行中です。
これらのデータからも分かるように、日本の対米投資は主に民間企業によるものであり、政府の税金が直接投入されるわけではありません。石破首相の1兆ドル投資計画も、こうした民間の投資活動をさらに促進し、日米経済関係を強化することを目的としています。
一方で、この巨額の対米投資に対しては国内からの批判も存在します。京都大学の藤井聡教授は、石破首相の対米投資計画について「米国に媚びて『保身』を図るための、おぞましき石破の『売国』行為である」と強く批判しています。藤井教授は、これだけの巨額投資を米国ではなく日本国内で行えば、デフレ脱却や生産性向上が実現すると指摘し、国内投資の重要性を訴えています。
また、藤井教授は「その投資は政府でなくて民間だからOK」という擁護論に対しても、「投資は国外より国内で行われる方がデフレ脱却等を通して国益に貢献するのは自明であり、それを誘導するのが総理の責務なのにその逆を石破は宣言したのです」と反論しています。つまり、たとえ民間投資であっても、政府はその投資先を国内に誘導すべきだという主張です。
このように、石破首相の対米1兆ドル投資計画は、民間企業の投資を促進することで日米関係の強化を目指すものですが、その投資先を巡っては国内で賛否両論が存在します。政府としては、対米投資の促進と同時に、国内経済の活性化にも十分な配慮が求められるでしょう。